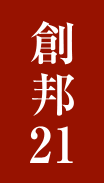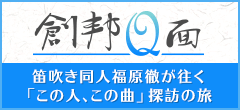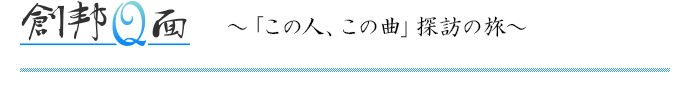

~笛吹き同人福原徹が往く「この人、この曲」探訪の旅~
第3面 清元栄吉の「触草~クサニフレレバ」
③
 ――さて「触草」ですけれども。篳篥とたとえば三味線とかね、それは編成としては、どうでしたか。やりやすかったとか、やりにくかったとか。もちろん三味線はご自分の楽器だから入れることは前提だったと思いますけれど。そのへんの組合せの苦心の点は何かありました?
――さて「触草」ですけれども。篳篥とたとえば三味線とかね、それは編成としては、どうでしたか。やりやすかったとか、やりにくかったとか。もちろん三味線はご自分の楽器だから入れることは前提だったと思いますけれど。そのへんの組合せの苦心の点は何かありました?
栄吉:やっぱりね、それぞれの楽器の持っている空気感というか、「広さ感」が違うんですよね。三味線の音がすると途端に四畳半みたいになっちゃう。
――ウッフッフッフ。
栄吉:お箏とお笛と篳篥とだと、いくらでも広い空間になるんです・・屋外に出られるんです。ところが、三味線が聴こえた途端に「障子とふすま」が出てきちゃう、みたいな。そういう意味で難しかったです。
だからっていうか、あの曲最初しばらく三味線ないんです。お箏のオスティナートの上でお笛が遊んでいる時間があって、なかなか三味線が出せない。
――清元の三味線弾きだから、なおさら気になるのかもしれませんね。
栄吉:(笑)とにかく、「草いきれ」がして「コーラン」が聞こえてきて・・っていう世界と、三味線の畳っぽい空気感、質感はものすごく合わない(笑)。
――曲の構成はどうなってますか。章立てしてあるけれども。・・・初演のプログラムノートに、「プロローグ」、「雨後」、「呪術」、「インターリュード」、「ダンス」、「彼岸」、「エピ口ーグ」の七つの部分から成っていると書いてらっしゃいますね。
栄吉:真ん中の「呪術」っていう部分、さっきちょっとお話したところね、あそこで全合奏になるんですけども、ひたすらおんなじ音型の繰り返しで。
間違わないように弾くの、必死なんです(笑)。
――でも聴いたかんじとして、三味線に全く違和感はなかったですけどね。
栄吉:イヤでもねえ。いちばん最初に三味線入ってくるとこ、やっぱり「アレ?」って場違いに感じますよ。
――そうですかね。これを伺って僕は、三味線もやっぱりアジアの楽器なんだなあと思ったんですけどね。
栄吉:ああ。そうやって聴いていただけるとありがたいですね。
――それをちゃんと作品の中で証明したというか。そういうかんじがしました。
栄吉:ありがとうございます。
――三味線の使い方も、なにか工夫をされたのですか。
栄吉:三味線の使い方として、「江戸浄瑠璃のイディオムの内側で」っていうスタンスと、完全に割り切っちゃって純粋に「楽器として扱う」というスタンスと、大きく二つあるわけなんですけど、この曲はもう後者の方に割り切っちゃってます。
ただね。僕としては、三味線らしからぬ勘所や手の動きは、絶対やりたくないんです。
そういう意味では自分としての「縛り」というか矜持はありますけど、だけど音楽的には江戸浄瑠璃とは何の関係もない。
――三味線の勘所的にはふつうのものなんですか?
栄吉:そうですね。あと手順もね。
――そんなにびっくりすることは起きていないと。
栄吉:変な手の動き方っていうのは一切ないです。ただ二挺の組み合わせでいろんなことができるわけですよね。それはすでに第一回の「はつ恋」でもそうだった。
――その二挺は調子は一緒ですか?
栄吉:一緒です、はい。前のときにもしゃべったと思うんですけど、三味線を二挺使うアイディアは、そもそも清元梅吉先生が作られた(「しづかな流」の中の)「独楽」っていう曲、あの名曲から拝借したのです。そういう意味では清元由来です(笑)。
――ああ、「独楽」。あれはいいですねえ。余韻がずっと残ります。
栄吉:いいですよねえ。ああいうふうに、いつでもそのまんまの時代やそのまんまの空気がふわっと出てくるの、すばらしいですよね。
あと、この「触草」に関して言えるのは、邦楽って二回以上おんなじことをくり返すの、嫌うじゃないですか。でもこの曲、基本オスティナートの音楽なので、繰り返しそのもので出来てるのと、ポリリズム・・三拍子と二拍子の組合せとか・・使ってます。
――それ、僕はむりやり使っているかんじはしなかった。それを「売り」にはしていないっていうか。
栄吉:もちろんもちろん。何度も言うけどぼくは食べる方の人間なので、こんな味にするためには、こういう風にした方が厚みが出るのかなあ・・とか、そういうふうに考えるので。
――うーん、これは僕にとって為になる話です。僕は食べる側のことを考えてないからなあ。