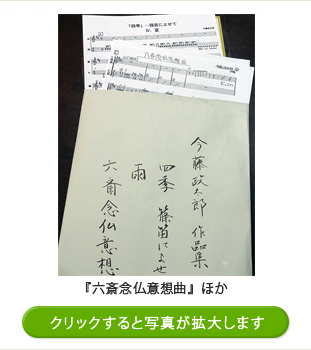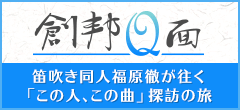笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月は世田谷区北沢の自宅稽古場に今藤政太郎を訪ねる。
今藤政太郎篇
その使命その覚悟 [前篇]

「思いつき人生」!?
――政太郎先生はお囃子の藤舎流お家元のお父上(四世藤舎呂船)と望月流お家元の家に生まれたお母上(藤舎せい子)を持ち、ご自身はお三味線に進まれました。三味線はお小さい時からやっていらしたのですか。
今藤政太郎:いえ、小さいときは唄だけやっていました。
――ではお囃子の方が先ですか?
政太郎:そうですね。子供の時は、亡くなった望月朴清さん(政太郎には従兄にあたる)やうちの姉なんかと会に出たりしてました。ぼくは専ら大鼓でしたけど。それとちょっと後に唄を習って。でもまあ戦争の空白の期間はあんまりできませんわね。戦後、京都に行ってから三味線弾きの伯母さんの所に遣られて習ってはいたけど、それの専門家になるとかいう気は全然なかった。父が会に出るときは聴きに行っていましたし、先斗町の筆香さんという名人の芸妓さんの唄が好きで、鴨川をどりによく行っていました。ちょうど、狐忠信が鼓のタポンって聞くと出てくるみたいに、裏の芸妓さんの声を聞いて、出ている!と思うとヒュッと行っちゃうんですよ。それから高校になって、父親が芳村伊四郎(十代目)さんの所へ稽古に行ってくれるかというので、伺ったのが高校二年。唄のお稽古です。そしたら伊四郎さんが「坊や、商売人になるかい?」って言う。そのころの人はプロって言わないで商売人って言ってましたね。それでどういうわけかぼくのことを「坊や」って言うんですよ。商売人になるかいって言われて、なんだかまんざらでもないような気がしちゃいましてね。
――ということは、唄うたいになろうと思ったんですか?。
政太郎:はい。初めからゴロがまわったし、間のオモテウラも使い分けられたんです。知らずに聞き覚えていたんでしょうね。それで商売人になろうかと思って、伊四郎さんに「どうすればいいんですか」って聞いたら「東京行って芸大に行きなさい」と。
――ははあ。
政太郎:でもそれもまた思いつきの人生なんですけどね。というのも、中学3年の6月から12月まで、ぼく結核を患って休学しちゃったんです。そのときに、滅多矢鱈に子供用の世界名作全集から父親の本棚から、とにかく活字が書いてあるものは全部読んだんですよ。それで、弁護士になりたいと思っていた。そこへ芸大って言われた。弁護士になりたい、でもなるには学力がなさすぎる。うーん。で、結果的にドロップアウトして、邦楽にいくことにしたんです。
――法律じゃない方のホウガクに行くことになったんですね(笑い)。ふつう本が好きだったら作家になりたいと思うんじゃないかと。弁護士は何だったんですかね。
政太郎:それはまあ、子供らしい正義感ですかね。でもその「坊や、商売人になるかい?」って言葉でね、ひとつはまだ大学も日和っていたこともあるんですけど、高校3年の冬に大学の願書を取って見てみたら、楽典もあるらしい。何も勉強してない。三味線も弾けなきゃいけない。で、一年見送り浪人して芸大に入ったんですが、芸大に入る前に、今藤先生のところに伺った。
――じゃあ、芸大に入るときは唄でですか?
政太郎:いえ。それもまたね、芸大入るなら三味線を弾けなきゃいけないとなって。まあそんなこんなで、ぼくは大学へ入る少し前に長十郎先生に入門したんですね。そのころは長唄の会でも地方巡演もしていて、「心泉会」っていう会が、ある時『娘道成寺』の全曲で地方を廻ったらしいんですね。その三味線を弾いていたのが(三世)今藤長十郎先生で、ぼくの父親も鼓で出ていた。全曲演奏っていうんで、柏伊三郎さんの作ったドドドン・・・の合方もやった。そこの三味線の間に鼓がトトスタスタスタスタスタストトンと裏打ちで入るんですが、父親が申しますには、大鼓がないからなかなか綺麗に入らなかったと。綺麗に入ってなくはなかったのかもしれないけど、父親としては気に入らなかった。3回くらいやって、満足がいかなかったんですって。で、4回目だかに初めて自分で「今日は上手くできたな」と思った。そしたら長十郎先生が「泰ちゃん(四世呂船のこと)、今日は上手くできたね」って言ったんですって。その言葉に父は「カチッ」ときた。こいつは!と思ったと。それでね、ぼくが三味線習うなら長十郎―やっちゃんの所に遣ろうと思ったんですって。そういうことで今藤に行くことになった。
――なるほど。
政太郎:ぼくは三味線で入学して卒業したら唄うたいでやっていこうと思っていたのに、いろいろ習っているうちに面白くなっちゃったんですね。しかもぼくとほぼ同時に入門した今藤長之さんがね、入門したてからすごい天才ぶりで、何でも一回で唄えちゃうんですよ。ああ、こいつには敵わないなと思ったこともある。あるとき、長十郎先生のおさらい会でぼくは「坊ちゃん」ですから『二人椀久』をやらしてもらった。長之さんは『汐汲』なんですよ。先生は唄うたいじゃないから高い声は出ないけど、『汐汲』を5本で必死になって、50分くらいかけてお稽古するわけ。それを見てね、ぼくは坊ちゃんだから椀久をやらしてもらえる。長之さんは先生がほんとうに「こいつに懸けた」っていう思いでいる。そう悟ったんです。それで、じゃあぼくはこいつの三味線を弾こうと思ったんです
それと大学の願書を遅まきながら取りに行ったときに、ついでに邦楽科ってどんなところかと思って、裏口からそっと入った。そしたら唄が聞こえてくるんです。忘れもしない、『橋弁慶』の「さても牛若は」っていうところでね、それがほんっとにいい声でうまい。うまいというかほんとうに貴公子が笛を持って立っている風情なんですよ。誰だろうと思った。それが宮田(哲男)さんだった。それでぼく、大学入って、ぼくは一番の「みそっかす」だったけど、将来この宮田さんの三味線を弾けるようになりたいと思ったんですよ。
――そうしますと作曲はいつごろからなさったのですか。何かキッカケは・・・
政太郎:あのね、長十郎先生のところにお稽古に行って一曲か二曲やっていただいた時に、どういうわけか先生が「お前は作曲をしなさい」とおっしゃったんですね。大学へ入る直前。何というわけでなく「お前は作曲するといいかもわからないよ、やってみなさい」と。それがどこかに残っていて、大学時代に初めて作ったのが『六斎念仏意想曲』。そして昭和37年にね、東京新聞の作曲コンクールに出品しろというのでやってみたら、なんか運のいいことにぼくの『能楽囃子による組曲』(現在は『~による幻想曲』と改題)が一位入賞しちゃったんです。それで、これがぼくの仕事だと思って、作曲するようになったんです。
一生の師に出会う
――長十郎先生が作曲をしろっておっしゃったのは、先生なりの何かを感じられたのでしょうかね。あるいは時代的な何か。それとも、ご自分が作曲をなさっていたから、弟子にもやらせようみたいなこともあったんでしょうか。
政太郎:どうなんでしょうかね。よく一期一会って言うけれども、ぼく、ほかのどんな先生に入門しても今の自分はなかったと思うんです。今の自分がどうこうって言えるような偉そうなもんじゃないですけども、少なくとも80歳過ぎまで現役の音楽家でいられたのは先生のお蔭です。そうねえ、先生も不思議なんですよね。教えるときに、弾き方の原則とかリズムとか、そういうのはうるさいんですけどね、曲の解釈とかは何もおっしゃらないんですよ。基礎は、ともかく一所懸命練習しろと。で、あとは自分で作るものだと。そういう教え方だったですね。――あんまり解釈論とかをおっしゃらない?作曲をする方ってむしろそっちが得意そうなかんじがしますけど。
政太郎:全然そうじゃない。でもね、ぼくがこの先生こそ一生の先生だと思ったと同時に、先生も何か、こいつはおれの一生の弟子になるかもしれないなと思ってくださったのかもしれません。結局三味線弾きになったのも、そういう縁っていうかね、なにか結ばれていたのかもしれないと思うんですね。
――三世長十郎先生は政太郎先生とおいくつ違いでいらしたのですか。
政太郎:ちょうど20歳です。入門したのが、ぼくが19歳で先生が39歳のときですから。やっぱり人には運というものがあって、そのひとつに時の運というのがあると思うんですけど、そのとき長十郎先生には自分の子飼いの弟子があまりいなかった。自分のワキを弾く人がね。先生がこれからさらに上がっていく上昇の機運にあったときです。
――お稽古は厳しかったですか?
政太郎:いいや。・・・不思議な稽古だったですね。ぼくは怒られることは殆んどなかったけど、訳のわからないことはよく言われた。
入門したばかりのころ、ぼくに「うまくなりたいか?」っておっしゃる。うまくなりたくないわけがありませんよね。で、それにはまずリズム感だと。テンポ感だと。音程感だと。それを良くして訓練すれば三味線はある程度は必ずうまくなる。でもその一つでも欠けたらうまくはならない。だからよく耳を傾けて、正しい音と、正しいリズムといいテンポをよく自分で覚えることだって、言われたんですよ。それであるとき先生のところにお稽古に行くと、先生が弾いて素人のお弟子さんが唄っていた。全然正しいテンポじゃない。あれ?ってぼくは幼いから思った。で、首を傾げてたんでしょうね、それから一週間ぐらい経ってからお稽古の帰りに「おい、ラーメン食べに行こうよ」っておっしゃるんですよ。そのころラーメン食べに連れて行ってくれるっていうのはもうたいへんなことなんですが、そのときに、「おまえは京都の高校出たんだろ」「そうです」「桂離宮見たか」「見ました」「どうだった」って。わかりゃしませんよねえ、「良かったです」「どう良かった」って言われて返事も何もできなかった。そうしたらね、「桂離宮の奥の書院の廊下は、その入口に立つと、真っ直ぐに見える。実はあれは末広がりになっていて、遠近法を逆手にとっていて、それで真っ直ぐに見えるんだ」って、それだけおっしゃるんですよ。その後つらつら考えて、なるほどぼくのしかめっ面のせいだなと思った。先生が正しいテンポでも正しいリズムでもなく弾いたことに対する婉曲な答えなんですよね。つまり、唄に合わせて弾くことって、それが正しいリズムや正しいテンポじゃなくても正しいんだ、結果的に音楽的な真実と物理的な真実は違うんだっていうようなことを言われたんだろうなとぼくは思ったんですよ。まあそんなようなことばっかりでね。
――ははあ、なるほど。
政太郎:ぼくはね、父親が長十郎先生と仲が良かった。ぼくがなぜ三味線弾きになりたかったかっていうと、囃子にはなりたくなかったから。父親の威光をもらうくらいだったら何もやらない方がましだと思っていた。それで三味線弾きになった。でもこれはぼくの若気の至りでね、そういうところでも七光り大ありなんだけど、若気の物分かりの悪さでわからなかった。でも先生は、泰ちゃんの息子っていうんでかわいがってくれたんだと思うんですよね。ぼくは先生が好きだったですし。好きだからやっぱり一所懸命やりますよね。それから何といっても環境がよくて、唄では長之さんがいて、三味線では今の淨貢さんがいて。淨貢さんとはもう、無二の親友か倶に天を抱かざる敵か、みたいな関係だったんですよ。一方、学校に行くと関さん、―今の貴音抄太郎さんが天才青年だったんですよ。そういう上手いやつばっかりがいる中で切磋琢磨してやってきたっていうこともあるし。練習は先生から強制されなくてもしたんですね。先生は禅問答のようなことを言っていればよかったのかもしれませんね(笑い)。
それとね、よく先生から夜に電話がかかってくるんです、うちがわりと近かったから。10時とか11時にね、「おまえ、用してるか」って言うんですよ。「ちょっと来い」と。何か怒られるんじゃないかと思ってこわごわ行くと、「いいお茶が入ったから」ってお茶いただいて、よもやま話して。「勧進帳ていうのは」とか「安達ケ原は」なんていう話はしないですよ。でもそのよもやま話からいろいろ教わったんですね。それと、舞台での相性が良かったと思うんです。ぼくは若いときに先生のワキを弾くのが嫌で嫌でしょうがなかった。『道成寺』みたいな大勢のものだとぼくはワキなんて弾けない。間に上の人がいるから。ワキに乗れるのは『高尾懺悔』とか『関寺小町』とかそういうときだけでね。
――先生とふたりで弾くときのワキですか。
政太郎:そう、それはもう、汗かくばっかりで撥なんか全然当たらないような思いです。嫌だったけれども、それが勉強になっていたわけですよね。まだ経験不足のところで、隣で弾こうと思ったらそりゃあなんとかしなくちゃならないでしょ。そのころ杵屋勝雄さんが先生のワキをよく弾いていらした。なんであの人は先生と一緒に撥が下りるんだろうって不思議だったんですよ。そのうち、先生も唄を聴いているしぼくのことも聴いている、ぼくも唄を聴いているし先生のも聴いている、同じことをしているんだ、だから一緒に弾こうとせず、一緒に曲に乗ればいいんだって思うようになってから、流し撥まで一緒に弾けるようになりましたね。そんなことで、ある部分で先生と一体化しちゃっていたと思うんですよ。
新作が盛んな時代
――長十郎先生の作曲のお手伝いをするっていうようなことは、なさっていたんですか。
政太郎:花柳界の踊りなんかでは何回かやりました。「ここ、お前やれ」みたいなね。
――そういうときに何かああしろこうしろみたいな具体的な作曲のアドバイスとかはされたり?
政太郎:まああんまりなさらないですね。台本読んで、これはこういう場面で、おれは後の所でしっとりさせるから、ここはあんまりしっとりさせないようにしろよ、くらいのものですかね。
――作ったものについて何か言われるとか手を入れるとかいうことはなさらなかったんですか。
政太郎:あんまりなさらなかった。寸法が違うからちょっと切れとかのアジャストはしていただいたけれども。ただね、日本的なメロディーで、やわらかいメロディーに困ったら今様を思い出してみろと言われた。あの『平城山』のメロディーだよと。それはいろんなところで役立ちましたね。ついでにぼくのネタばらしをすると、京都で地蔵盆っていって、お盆が過ぎてから子供ばっかりをお地蔵さんの前で集めて、お数珠を廻して御詠歌を唱えて、行くとお菓子がもらえるのがあるんですが、その時の御詠歌がぼくの中に今もすごく残っていて、いろんな曲に使っています。ぼくの教会音楽みたいなものですね。――そのころから邦楽界は新しい曲を作ることが盛んな時期になりますよね。
政太郎:ちょうどそういう時期になって、ぼくはさっき言った東京新聞のコンクールに入賞してから作曲の依頼が来るようになった。それが27歳のときです。それから30歳代、ちょうど舞踊の新作ブームがあって、営業作曲が年に10曲ぐらいありましたね。――その時期、いろんなところで皆さん作られてますし、各放送局が芸術祭参加でそれぞれ邦楽の新作を作ってましたね。こんな同じような時期にまたずいぶん同じようなメンバーで作っているんだなあという印象を受けますけれども。あれはやっぱり時代のニーズなんですかね。
政太郎:そうですねえ。長十郎先生の「創作邦楽研究会」もあって、先生、その下に梅吉さんと英寿さん、その下に巳太郎(淨貢)さん、伊十七さん、ぼくと続いていて、次々作っていましたねえ。また放送局もNHKといわず民放といわず、芸祭というと必ず出品するんですよね。そのひとつが『日月星』とか、長十郎先生の『こころの四季』とか梅吉さんの『しづかな流』とか。こないだ再演した創邦21の『からんくにゆき』と同じ題材を扱った『じゃがたら文』っていうのもあったし。毎年もうたいへんな騒ぎでしたね、30分の曲を録るのに一週間、毎日5時間も6時間もかけて。――古典の演奏もあるでしょうし。
政太郎:そう、それもけっこう忙しい。区分けでいうとぼくらは新曲人種なんですよね。なのに世の中っていうのは不思議なもので、新作を作曲すると古典の踊り地やなんかもうまいと思われる。でもそんなことない、なんにも知らないわけです。その都度ドタバタしましたけど、でも恵まれていました。――作曲はもちろん依頼されてなさることが多かったのでしょうけれども、作ることそのものは、嬉々としてなさっていたわけですか?
政太郎:正直言って嬉々とはしませんでしたね。これが僕の仕事だという思いはあったけれども。「あ、作曲できる、嬉しいな」というのではなかったですよね。それで常に、こんなふうにできないのは台本が悪いからだ、あれが悪い、これが悪いって人のせいにしてましたけど(笑い)、ほんとは自分が悪いので、あの『ぼくが作曲できない理由(わけ)』、あれですよ(笑い)。――フッフッフ、そうですか。作曲の話が出てきましたので、後篇で作曲家今藤政太郎に迫ることといたします。
・・・後篇につづく