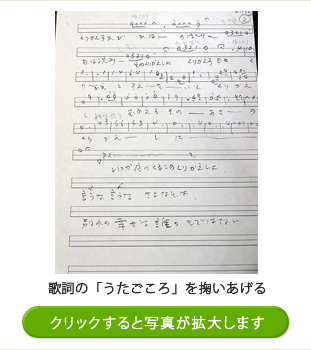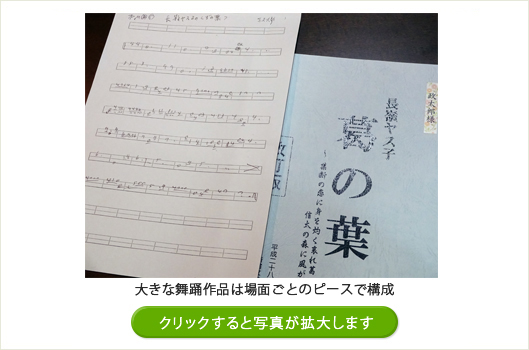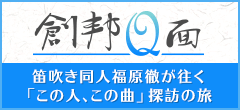笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月は世田谷区北沢の自宅稽古場に今藤政太郎を訪ねる。
今藤政太郎篇
その使命その覚悟 [後篇]
作曲の実際
――実際何曲くらいお作りになっていますか?数はわかりますか。
政太郎:わからない。何回も作曲年表こしらえようと試みるんですけどね。最近になって、ああもう命は長くないから少しはそういうことも気に懸けなきゃなと思い始めてきたんですけど、目の前にあることをしたらもうそれは預金残高にならなくていいんじゃないか、そういうタイプなんですね。言えば「あとは野となれ山となれ」。
――(笑い)先生、B型でしたっけ?
政太郎:B型。B型はそういうもんですかね?
――いやわかりませんけど(笑い)。
政太郎:そういうあなたは?――ぼくはA型ですけど。
政太郎:あ、そうでしょうねえ。・・・だからね、何年に何を作ったとかね、あんまり覚えていないんです。でも圧倒的に舞踊曲が多いです。作曲って想像している時間が一番嬉しくて、実際の作業にかかったら苦しいし遅々として進まない。またその時間が圧倒的に多いわけですよね。つまり、ひとつの箇所について選択肢を五つも六つも持っている時は進まないわけですよね。結局選択肢を絞らざるを得なくなって、筋がもう1本とか2本とかになってしまったら、あとは早く進みますね。それまでが、もうね、夜中でも寝てても寝てなくても、考えてましたね。作曲していて脂汗が出るんですよ。それで異常な興奮状態になる。
――それはどの段階ですか。
政太郎:いつかなあ。態度は一心不乱には見えないけど、脂汗をかいてるのね。あるところまで行くのが長いわけ。で、いったんほぐれると、わりとそれからはまた止まるにしてもいける。ぼくは頭が理数系ではないから構築的な曲は作れない。つまり縦の線では作れない。やっぱり横の線で作って、それに縦の線を足していくっていうかんじですね。自分のリズムで構築するというよりは、「うた」で奏でるような曲を作ってしまう。
――さっきからお話を伺っていて、「うた」になにかフォーカスされているというか、政太郎先生の中でうたに対するあこがれのようなものがおありだし、先生の作品にもそれがすごくあるような感じがします。三味線の方なのに唄に対して愛情が強いというか、そんな印象があります。
政太郎:そうかもしれませんね。器楽の曲を作ってもやっぱり三味線がうたう「うた」になるし、『六斎念仏』のような純器楽曲というか太鼓のための曲でも、やっぱりどこかにメロディーが漂わないといられないんですね。
――あるところまで考えて、作り始めるともう一気っていうかんじですよね。それは後でどのくらい直すのですか?いつまでもいじくるタイプですか?
政太郎:そんなにいじくりはしない。ぼくはよく錯覚を起こすんですよ。というのは楽器を持たずに作るから、頭の中で勝手に転調しちゃってたりするんですよね。だから途中から4度違いとか5度違いで作っちゃってたりということがあって。
――ああ。弾いてみたら違っていたっていう。
政太郎:そう、それを直す。それから拍の取り違え。拍の長さが違っちゃっていたり。
――その、三味線使わないで作曲するのは昔からですか。
政太郎:ビギナーの時は三味線を使ってました。でもあるときから、とくに依頼されて舞踊曲を作るときなんかに、三味線を持つ暇なく作っちゃうっていうところでね。ただ、三味線を持つと、想念ではできなかったけれど楽器が教えてくれるってこともありますわね。楽器持った方がいいなと思う時はもちろん持ちますよ。持たないのがポリシーなのではなく、持たないのが習慣になっちゃったっていうか。
――政太郎先生は洋楽、たとえばピアノとかは習ったんですか。
政太郎:ピアノは芸大ではずっと可でした(笑い)。ちゃんと習ったことはないです。
――いわゆる楽器を使わないで作曲するためのソルフェージュの訓練みたいなもの、絶対音の訓練とかそういうものは・・・
政太郎:それはないです。いまだに絶対音はないですしね。
――つまり、古典的な邦楽の感覚のみで、なおかつ三味線なしで作曲が可能であるということですよね。
政太郎:そうですね、それは母の膝枕ですね。お稽古している母の膝でいつも寝てて、その間に口三味線も覚えたんですね。で、今もお囃子の人に「袖を返しておもしろチリンリリン、ハ、チャンチャンチャン、あり、ハーオ、天天、フ、ヨイたかまが、ツ」って言うと、望月の系統の人はみんな、自分の知ってる『雛鶴』の覚え方とまったく同じだって言う。それを四つとか五つとかの時に覚えているわけね。言うなれば、そのころから邦楽に関するソルフェージュをやっていたからなんじゃないかと思います。
伝統をどう捉えるか
政太郎:ぼくねえ、父親に反発してたんだけど、芸ではむしろ父親の影響はものすごく大きいですね。たとえば、ぼくが昔自分で『時雨西行』をお稽古していたとき、「弓矢を捨ててぇ、ド・ト・テ、墨染めに」とこうやってたら「バカヤロ!」って怒られた。「なんでですか」「お前ね、西行法師は衣の下に刀挿してたのか、弓矢持ってたのか。弓矢を捨ててっていうのは、武士の道を捨てて仏門に入ったってことじゃないか。だから象徴的な意味なのに、まるで実物を捨てるようにやるのは違う」と、こう教えてもらった。それから、うちのおやじはほぼ古典の形のものをやっていて、古典からはみ出たものも少しはやっていたけど、でも伝統の様式にうるさかった。
それがね、日生劇場で有名なモダンバレエダンサーの石井かおるさんが『黒髪』を踊るので一挺一枚でやってくれというので、ぼくと(今藤)美知とでやったとき。父親が舞台稽古をいっぺん見てみたいというので来たわけ。真っ暗な舞台で、上手に燭台がひとつ置いてあって、そこに一挺一枚、ぼくらがいるわけね。その燭台に向かって、下手からサーと石井さんが入ってきて燭台の前で腕をこうしたときにチャンと始まる。ま、そのときわりといい演奏ができた。そうしたら親父が美知に「バカだなお前は!」って怒った。それは、唄う前に扇を取ったと。燭台と石井かおるさん以外何もない時に、お前が扇を取る動作をしたら、みんなそっちに目が行っちゃう、こんなに緊張していた糸が切れるじゃないかと。唄っていうのは扇持たないと唄えないのかと。そんなのは形式に過ぎない、そんなこともわからないのはバカだと言った。おやじも美知もぼくも、こういう場に遭遇するのは初めての経験なのね。しかしこういう場面で、様式とされているものを良しとするか、そのときの芸術的な緊張が大事か、それを一瞬のうちに悟れないようなやつはバカだと。ぼくも実は言われて初めて気がついたから同じようにバカなんだけど。父親は囃子の家元で、一番様式っていうものに拘らなければならない立場の人間でしょ。そのときにおやじってすごい人なんだなと思った。
また『時雨西行』の話をするけれども、おやじの鼓っていうのは、チチチリチチチン チチチチツン、タポ、それだけで秋の風情がふわーっと見えるわけ。残念ながら三味線がチャンと弾いても、唄がアと唄っても、完結した世界っていうのではないよね。でも、ぼくの父は、まあ身びいきかもしれないけど、ポン と打つとそのひとつの音の中にちゃんと世界があった。それは鼓なりゃこそでもあるんだけども。そのかわりぼくは、プロになろうと思ってやりだしたとき、まあ父も母も商売人だし、周りはみんな上手い人ばっかりだし、「お坊ちゃんお上手ですね」って言われることなく(笑い)、おれは下手だ下手だと思いつつ過ごしてきたからね、コンプレックスの塊のまま80年、正確に言えば60年ちょっと、過ごしてきたわけでね。
――なんとなく邦楽の人って偉くなっちゃうと守りに入るようになるように思うんです。別に若い時と同じようにする必要はないと思うんですけど、大曲じゃなくたっていいですし、弾かなくたっていいわけですし、絶えずチャレンジしてくださるとぼくらもそこから刺激を受けるだろうなあと思うんです。
政太郎:ぼくね、大恥かくのは好きじゃないけども、でも案外間違えたり失敗したりするのは当たり前だと思っているのね。だって、今現存している曲の何十倍も曲ができていて、ほとんど失敗作だったわけだよね。だから、失敗を恐れる必要はないと思って。それと、いつも言うことなんだけど、ぼくは教師にはなれないけど反面教師にはなれると思っている。たとえば今度「復曲」―歌詞だけ残っているところに、こうかな、ああかなって考えて復元的に作曲することをやりはじめたんだけども、そういうアプローチの仕方もあるよと。そういうアプローチをすることによって、オリジナルの作曲もうまくできるようになる。逆に、新作を一所懸命作ることによって古典の演奏もうまくなる。そういう相互作用っていうものがあると思ってね。
また伝統のことでも、昔はこうだったからこうしなきゃいけないという考え方、それも正しいんだけどね、そうじゃなくて、もしモーツアルトが江戸時代に日本に来て長唄を作ったらどんな曲になるかとか、九代目六左衛門や三代目正次郎が今いたらどんな曲を作ったろうかとか、伝統を固定的に見ないで、そんなようなことを考えるのもおもしろいんじゃないかな。ほんとは若い人からそういう発想が出なくちゃいけないんだろうと思うけど、なかなかそういう機運が生まれないんだったら、まあおっちょこちょいやって、ちょっと火中の栗を拾ってみようかという気がしましてね。
そんなことをやってみたら、年の功でね、有力な人たちが集まってくれてプロジェクトチームが生まれた。ありがたいことです。
年を重ねて思うこと
――「創邦」の若い人たちって、どんなふうに見えるんですか。
>政太郎:一口にいうとね、もっと喧嘩をしてほしい。
――ハッハッハ。
政太郎:もっと口角泡を飛ばしてね、議論してほしい。最初のころ、みんなでテープを持ち寄って聞かせて、それを褒めるなと。褒めないで欠点を洗い出そうってなっていた。それがいつの間にか緩くなっちゃってるように思う。それから、大事なのは作曲の仕方じゃなくて作曲の態度と思うんだよね。そして結果的にはもっと失敗していい会だと思うんだよ。――個人的な興味から伺うのですけれど、お囃子の曲を作ろうというお気持ちはないですか?というのはね、創邦でも一般の踊りの会でも、みなさん作曲されてそれをお囃子の方が作調すると、なんだかお囃子を入れたがためにみんな同じように聞こえちゃうように感じて、素で聴く方が却って個性がはっきりするなあと思うときがあるんですね。だから、もちろん囃子のことは囃子の人が作ったほうがすんなりできるとは思うんですが、もうちょっと、作曲者本人が一部分でもいいから作調するなり作調方針なりと示すと、その人らしい曲になるんじゃないかと思ったりするんです。政太郎先生の場合は、やっぱりお囃子をものすごくよくご存じでいらっしゃるから、たぶんおもしろいのができるんじゃないかと思うんです。たとえば極端な話、鼓の一丁の曲でもいいし、メロディーがお好きだからメロディーがないのはお嫌かもしれないですけど、でも今だったら打楽器だけの曲とか、もし作られたらどんなのになるんだろうなあって。
政太郎:あのねえ。ぼく、お囃子のことは大して詳しくもないのに手組っていうものを知っちゃってるわけですよね。そこがぼくのアイロニーになっていて、下手なことをするんだったらやってもらった方がいいやって思う。それとね、ひとりで何でもやると偏っちゃいますよね。もしいろいろ知っているからっていうのでぼくがお囃子の曲を作るとしたら、すごく易しくするか、あるいは逆手をとってチリカラスットン、ピ、とかね(笑い)、つまらないことをやっちゃうと思うんですよね。それともうひとつ、ぼくは書くのが遅いから、そこまで手が回らないということもあるのでね(笑い)。――大作というのでなくても、たとえば練習曲的なものでもいいと思うんですよね。囃子の曲で、伴奏というか囃子の合間に三味線や笛が入るとかいったもの、それも易しいもの。趣味でやってる人が友達同士でちょっと楽しくやれるようなもの。そういう曲って、政太郎さんじゃなきゃできないんじゃないかなって思うんですけどね。
政太郎:おだてに乗っていっぺんやってみます。でも、鼓の人が打とうと思ったら手の甲で打たなきゃならないようなのを作っちゃうかもしれないよ(笑い)。
――そのー、専門の楽器の曲だと、どうしてもある種の極限状態の作品を作っちゃうじゃないですか。おれが打てる、おれじゃなきゃ打てない曲だ、みたいなところを作ってしまう。逆にご自分が鼓を打つ立場ではないからいいんじゃないかと思うわけです。
政太郎:確かにぼくだって『六斎念仏』なんてのは自分がたいして弾けやしない時分、ある意味手はよく回ったけどそれだけっていう時分に作ったわけだからね。どうだい、こんなの弾けるか?っていうような気持ちが何パーセントかあった。そういうところからほんとうは離れないといけないよね。――ご自身では、これから自由に作るとして、どういうものを作られたいですか。おっしゃるように人生の、少なくとも若手ではないですよね、そういう段階に来て、どういう曲を作りたいか。今までと方向の違うものを作りたいとか、そういうものって何かありますか。
政太郎:ぼくはランダムに作るんですよね。だからある構成を以って作るっていうわけではないんですけどね、ただ、古典の形の曲がぼくは今まで少ないわけで、それで去年から始めたことがある。古典でも、今の歌詞でただ今の僕の感性で作る古典の形よりも、もうちょっと歳をとったからこそできるものとか、あるいは生意気な言い方だけど、人の指針になるようなものを作りたいと思いましてね、それで去年から、さっきちょっと話に出た「復曲」をね、古典の「復曲」っていうのをやっているんです。それはね、たとえば1705年にあったものを、あった通りにそっくりに復元はできっこないですよね。譜面もないし。でも、できたら、その時代の様式、歌舞伎の様式、まあそれも含めての時代の様式なんですけれども、それから作曲者の様式あるいは作者の様式、そういうものを推察しながら迫っていくことでもって、それを復元する。復元するだけじゃなくて、そのころの曲っていうのはどういうものを目指していたんだろう、それがどういうふうに今に至ったんだろうかという、系統的な曲の変遷っていうかな、そういうのを辿るってことなんですよね。逆説的にいうと、ぼくは、新曲の創作をすることによって、自分自身演奏がうまくなったと思うんです。つまり気がつかなかったところに気がついて、技術以上の演奏ができるようになったと思うんです。その逆。そういう古い人が作った様式を推察して作ることでもって、今の時代に、新しいものにそれがなんとかフィードバックできないか。
もうひとつぼくはね、作曲とかなんとかではなくて、なんでぼくこんなに日本の音楽が好きで、一所懸命やってるんだろうな、食うためだけじゃないよな、なんでなんだろうっていうことをね、自問自答してるときなんですよ。
いろいろなところで話しているんですけど、日本には擬態語とか擬音語っていうのが非常に豊富です。たとえばぼくの『雨』っていう曲には雨の擬音語をいっぱい入れているんですけど、雨の音って、ざんざんだったり、ざあざあだったり、しとしとだったりするわけですわね。なんで雨の音がそんなにあるのか。もっとおもしろいと思うのは、「泣く」。わあわあ泣く。えんえん泣く。しくしく泣く。めそめそ泣く。涙が落ちるのにそんなに音があるわけじゃないですよね。なぜなのかなと。それでぼくが思うに、日本人は涙にも雨にも感情があって、その時に置かれた状況の声を発すると思っているのだと。ということはなんだろうか。そうか、やっぱり八百万の神がいて、人それぞれに神であり山川草木すべてが神だという考えが根強いからなんだろうなあと。ではなぜそうなるのか。それはまたわからないんだけれども、まあ気候風土、そういうものが日本の風土にずっと根付いていて、絶対的な勝者、絶対的な弱者を作らない文化なんじゃないかな。で、実はその文化がやっぱり今となっては愛おしいのかなあ、そんなふうに思っている。それがぼくの音楽観にもどこか繋がっているんじゃないかと思っているんですよね。
実は今年も12月10日に自分の発表会をやるんですけれども、そこで折口信夫の『死者の書』をやろうと思っているんですよ。どうやって音楽台本にするかっていうのが難しいんだけど、その『死者の書』を一読したときに是非曲にしたいと思ったのは、「した、した」っていうところなのね。大津皇子が蘇る時に聞こえてくる音ですよね。それに引かれてやることにしちゃったんです。
――それは楽しみですね。
政太郎:ありがとうございます。しかもそのときに「復曲」もやるんですよ。プロデュースもするし、ぼくも作るし。――お作りになってくださるというのはとても心強いです。
政太郎:いやいやいや、それしか能がないからさ。(2017年1月5日 北沢・今藤政太郎自宅稽古場にて)
ききて:福原徹、記録:金子泰
・・・番外篇につづく