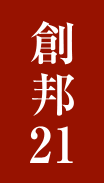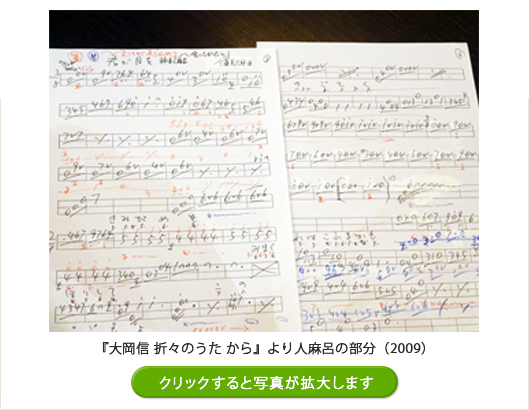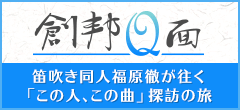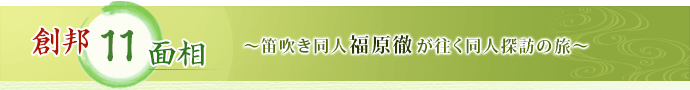
笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月はコートヤード・マリオット銀座東武ホテルに今藤美治郎を訪ねる。
今藤美治郎篇
こだわりと美意識ゆえの [前篇]

長唄と絵と
――創邦の人はほとんどそうなんですけど、美治郎さんはまたおうちがすごく長唄一族で。でも絵の方もなさったんですよね。
今藤美治郎:いや、なさったってほどのものじゃなくて、でもまあ絵も好きだったのと、結局図画工作の点数が良かったがためにちょっと興味があって、(大学を美術の方で)受けるだけ受けてみたんですね。
――今でも似顔絵をお描きになったりとか、邦楽界の中では知る人ぞ知るというか、ある会では、みんなの似顔絵を描いた手ぬぐいが出ていたりとか。ぼくも描いてもらったことありますけど、
美治郎:そうでしたっけ?
――大学生時代に(笑い)。あれはもう趣味のレヴェルではないですよ。でも小さいころから長唄はやってらしたんですよね、もちろん。
美治郎:やってましたねえ
――それはべつに嫌とかそういうわけではなく?
美治郎:あんまり自分の意思がない子どもだったから、別に反抗期もそんなにあったわけじゃなくて、祖母(今藤綾子)に習っていて、行かないと電話がかかってきて「見放しちゃうよ」と言うんですね。で、見放されちゃいけないような気がして。それで行ってた。それにしても祖母は、ほんと根気があったなあと思いますね。だって今思えばもう歌詞の一行くらいをもう延々とやって、覚えなくて、そのうち足が痛くなってそれどころじゃなくなって、「一ぺん立って」って言われてエエまだやるのって思って、やらされて、でも翌日にはもう忘れてるって、もうそれの繰り返しをずっとやってくれていて。姉(今藤郁子)には相当厳しかったみたいですけどね。
――最初から三味線ですか?
美治郎:子どものころは唄ですね。最初は唄をやらされるわけですね。ぼくは子どものころからあがり症っていうか「緊張しい」だったんですけど。今の子って全然あがらない。すごいなって思って見ていますけどね。
――ごきょうだいのうち、美治郎さんは一番下で、上のお二人(今藤郁子、富士田新蔵)がなさっていて、嫌じゃなかったですか。
美治郎:あんまりそういうのはなかったですけど、常にいろいろ言われているし・・・いやいや身内はすべてね、褒めることはないわけですから。
――では小さいときはとくに好きというわけでもなく、また逆らうわけでもなく?
美治郎:そうですね。言われるがままに。
――で、絵の方に行きたいとは思ったわけで?
美治郎:ちょっとだけね。それも、試験を受けに行ったときに、周りの受験生を見て圧倒されたのは覚えてます。でも自分であんまり個性がある方だとは思っていなくて、その時もそう思っていたし、ちょっと憧れてたんですかね。・・・(サーブ係が取り分け用のお皿を持って行ってしまったのを見て、人を呼んで)さっきね、お皿を置いといてくれたのは分けるためだったのね。もう一回持ってきてくれる?(見送って)あの人じゃなかったかな。あたまのかたち(髪型)が同じだと見分けがつかない。・・・いや、いろいろ気になっちゃう。それで文句ばっかり言っているって、(奥様の杵屋秀子さんに)また怒られちゃうんですけど。
――そのへんが美治郎さんってすごくアーティストだと思うわけです。
美治郎:・・・。
作曲へのとまどいと開き直り
――曲を作るっていうのはもともとは興味はなかったわけですか。
美治郎:なかったですね。――じゃあ作り出したのは創邦に誘われてからですか。
美治郎:その前に政太郎さんに、吾妻さんの新作だったかな、「んんん、ちょっとキミも、んんん、やってみないかい(政太郎氏の声色で)」って言われるがままに、いついつ作曲するからっていうので行ってみたものの、もう沈黙状態で。だいたいその、「一緒に何かその場で」なんていうのが苦手なタイプだから、みんながいる中で作るなんていうのは、どうもね。その後もう一回舞踊協会の新作を、「やってみないかい」って言われたから、やらしていただいて。それはまだ踊りがついたらどうなるかみたいなことは全く考えられず、(作曲したものを)結構直されたりもしました。そういうことはありましたけどね、あんまり作りたいなって思いがありませんでしたよね、そのころは。で、創邦に入らないかって声をかけてもらって、最初は試演会みたいなことでやっていたのが、それがいきなり演奏会するみたいな話になって、ちょっとびっくりしたんですけどね。自分が作曲を習うためみたいな感覚で参加したのでね。そういう勉強の場になるのかなと思ったらそうじゃないっていうね(苦笑い)。でもしょうがないって思った。最初の何曲かでもう嫌になっちゃってるかんじはあったんですけどもね。・・・やっぱりなんかこう、新作というと新しいことを考えなくちゃいけないんじゃないかとか。難しいことをしなきゃとか。最初そんなふうに思ってましたのでね。
――今藤さんっていうと、長唄の流派のなかでも創作をよくされるイメージがあるんですけれども。先代(三世今藤長十郎)がたくさん作られて残されているし。その中で自然に作るふうであったということではなくて?
美治郎:ないですね。で実際作ってみると、古典にしろ何にしろ、よくこんなフレーズが出てくるなとかね、なぜ同じポジションばっかり使っているのにこんなに流れに富んだ曲になるのかとかね、すごく思いましたよね。引き出しの中を探しているかんじですけど。それがちょっとやる気になったのは、ある時、もういいやと。難しいのじゃなくていいだろうと、わかりやすく楽しいのにしましょうやと。そう思ったんですね。昔話の『ねずみ経』をどう作ろうかって考えていたときに、自分も楽しくなるような―まあ実際はフレーズも出てこないし苦しいですけど―、わかりやすくて楽しい曲があってもいいのかなというスタンスになって。それからは、自分でも少し変わった気がします。今はまあ、読解力には乏しいけどホンをよく読んでその場からイメージするっていう、やや「当て振り」的なかんじの作り方なんですけどね。あとは昔話だとどうしても『まんが日本昔ばなし』のイメージになっちゃうけど、あの空気感っていうか、あの色っていうかな、それを別にしても子守唄的なっていうかな、そういう日本の旋律なんていうのは、なんとなく思い浮かんでいるようなところはありますね。
好むところ
――ぼくからすると意外なんですよね。絵をお描きになって、しかも今藤さんだから、どちらかというとアーティスティックな方というか、いわゆる古典的な長唄ではない方に行きたがっているのかなと思いきや、そうじゃなくてむしろある種確実というか、そういう方に行こうとなさっている。でもたぶん根底には複雑なものがあるんじゃないかと思うんですけど。・・・古典ではどんな曲がお好きですか。
美治郎:けっこう杵勝の曲とかね、メロディックな、手事のおもしろい曲が好きかもしれませんね。たとえば、そう『五色の糸』。それから『梅の栄』とか『喜三の庭』とかも好きかなあ。もちろん他の曲もいろいろ好きですけど、合の手がたくさん入ってる曲に惹かれてますね。
――ああ、器楽的っていうか。
美治郎:うんうん、そうですね。それの一番衝撃的なのは、『老松』の松風の合方のあの替手との絡み具合ね。これ、なんなんだろう!?っていう。初めて聴いた人は相当気持ち悪いと思ったんじゃないかなと思うくらい。あと興味あるのは、主旋律じゃない、編曲的なこと。これは長唄に限らずに普通に歌謡曲とかを聴いていても、そういうバンドのアレンジの方が耳に入ってきたりしますね。
――たとえば『助六』に『六段』が入っていますけど、それも面白いと思いますか。
美治郎:あれはもう、はなから教わっちゃってるから、おもしろいっていう感覚よりもそういうものだって聞いちゃうけど。
――それじゃ、三味線同士のアンサンブルみたいなものが?
美治郎:そうですね。興味が向いているのはそういう方ですね。
――現代曲はお好きなんですか。杵屋正邦さんの曲とか。
美治郎:なんかやっぱりねえ、あまりにも拍子のない、現代っぽい、間をためてひとつだけ音を出すとかっていうのは、ぼくにはどうも・・・物語や映画の伴奏としてそういうのがあるのはいいんだけど、曲として楽しむっていう感覚はないのかもしれないなあ。絵でもわりと抽象画よりも写実画が好きっていうところもあるし。もちろん延びたり縮んだりはあるにしろ、拍に収まっている感覚じゃないと何となく嫌だなっていう。でもま、他の方が作っているのを聴くと、いろいろ、音の鳴らし方もそうだけど、空気感もそれぞれでおもしろいなって思いますけどね。
――画家でお好きな方は?
 美治郎:お、そこ行きますか。好きなのは、画家は?と訊かれたらアルフォンス・ミュシャ。そもそもあのひとの絵は、タバコのポスターを見たんですけど、好きなこだわりは曲線とデザイン化されている装飾物とか、女性の顔の輪郭、ラインとか。それだけがまた太く描かれていたりする、それが非常に好きで。でもそのー、・・・(フト思い出したように)これは「好き」と断言しましたね、ぼくにしては珍しく。
美治郎:お、そこ行きますか。好きなのは、画家は?と訊かれたらアルフォンス・ミュシャ。そもそもあのひとの絵は、タバコのポスターを見たんですけど、好きなこだわりは曲線とデザイン化されている装飾物とか、女性の顔の輪郭、ラインとか。それだけがまた太く描かれていたりする、それが非常に好きで。でもそのー、・・・(フト思い出したように)これは「好き」と断言しましたね、ぼくにしては珍しく。
――美治郎さんはディテールに惹かれるんですかね。さっきの松風の合方にしても。なんともいえない組み合わせみたいなのに惹かれるのかなあって今思ったんですけどね。
美治郎:一番惹かれるのはね、本手がチリリン、チリリン、チリチリチン・・・ってやっているのと重なっているところ。うん。あそこはもう聴いていても演奏していても気持ちいいってかんじになってますね。あそこは特に気に入ってますね。――創邦で美治郎さんが発表した曲って、ほとんど唄ものというか昔話的なものが多いですよね。で、さっき合の手がお好きっておっしゃった、たとえばその三味線の二重奏の曲をお作りになろうとか、そういうのはないですか?
美治郎:ないですねえ。部分的にそういうのが入っているのがいいんだって思う。だから器楽曲での三味線二重奏みたいなのを作りたいとは思わないですね。――やっぱり長唄でありたいっていうんですかね。長唄の合方でありたい、という。
美治郎:そういうのがあるのかもしれませんね。・・・後篇につづく