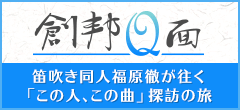笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月は銀座ライオンに松永忠一郎を訪ねる。
松永忠一郎篇
古典的スタイルにこだわる理由 [前篇]

曲を作るのに理由ってないですね
――そもそも僕が常々思っていたことなんですけれど、創邦の同人たちって古典曲の演奏だけでも覚えたりなんだりで十分忙しいはずなのに、なんで時間も労力も割いて新しいものを作るのかと。でまた、なぜ作るかってことは、あんまり皆さん表だって言わないでしょう?同じ同人のよしみで少々失礼なことも訊いたりして、そんなところを炙り出していこうというのが、この企画なんですよ。でね、僕から見ると忠一郎さんは創邦の中である種一番古典派の人、古典の演奏家のイメージが強い。それがああいうおもしろい曲を書く、しかも用意周到にちゃんと毎回暗譜してくる。それで第一回は忠一郎さんに訊きたいと思ったんです。「なぜ作るのか」?
松永忠一郎:曲を作るのに理由ってないですね。なんかこう衝動的なものですよね。
――ご自身は作曲って創邦に入る前もやっていたのですか?
忠一郎:やっていました。中学くらいからバンドをやっていたんで。友達が授業中に歌詞書いて、それで帰りにそいつんちに行ってギターでああだこうだやって。中学くらいのときは三味線そっちのけでギターばっかりでしたね。三味線やりなさいってあんまりうるさく言われなかったので、自由に、やりたい方向にやってました。 バンドを組むと、始めのうちは有名な曲のコピーをやるんだけど、そのうち自分たちで作りだすじゃないですか。僕らもそんなかんじでしたね。それでまた高校くらいから三味線に戻って、そのままこの業界に入ったわけですけど、音楽を自分で作ることに関しては、その流れで違和感はなかったですね。楽器を弾くんだったら自分で曲を作るのが当たり前っていいますかね。
――三味線で曲を作ったのは、創邦に入ってからですか?その前からご自分で作ってらしたのですか?
忠一郎:創邦に入る以前に、三味線だけの曲をちょっと作ったりもしたような気がします。といっても、本格的に一曲全部作ったわけじゃなくて、まあ断片というかスケッチ程度でしたけどね。でも、三味線弾きになった以上は、もちろん自分で曲を作って弾きたかったし、そうするものだとも思ってましたから。でも、やりたいって気持ちはいっぱいなんだけど、どうしていいかわからない。作るためには古いものを知らなきゃいけないと思って、ちょうど縁もあったので地歌を習いに行ったりしてましたけど、環境がまだまだ整ってなかった。作りたい、でもどうしよう・・・って、やりたい気持ちだけずーっとあったんです。
でも、これが好き
――忠一郎さんは創邦の設立からのメンバーですよね?
忠一郎:そうです。創邦21という名前で会が発足する前に、最初は政太郎先生に京都で呼ばれたのだったかな、そのあと東京でまた呼ばれて行ったら、淨貢さんもいらして、文字兵衛さんとか清元美治郎さんとか何人かもいらしていて、「今度、創作の会を作ろうと思うんだけども、みんなの意見を聞きたい」みたいなことで、ひとりひとり意見を言いました。
――それから少しして創邦が始まったんですよね。
忠一郎:そうです。僕は、さっき言ったように、政太郎先生からお声をかけていただく前から長唄でも曲を作りたかったんですけど、でも長唄は歌詞があるし、ちゃんとした形式がある。格がある。作るにはまずいろいろ知らなくてはいけないとも思ってましたし、そうそう思いつきだけでできるようなものじゃないですしね。創邦に入ったけど、しばらくはどうやって曲を作っていいのかわからなくて、何もできなかったんです。そこへ後から金子さんが入ってきて歌詞を提供してくれて、僕にとってはこんな幸運なかったですね。だから『梅若涙雨』がほんとの処女作。この出会いというか、これがなかったら、ちょっとどうなっていたかわからない。それだけ僕にとって創邦って大事で、人生の、今までぬかるんでいたものをちゃんと固めて一本の道にしてもらったみたいな感じがあります。導いてもらったといいますか・・・。
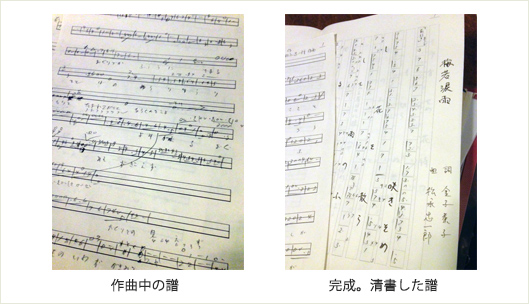
――忠一郎さんが作りたいって思っているのを政太郎さんは知っていらしたのですかね?
忠一郎:いや、多分何もご存じなかったと思いますけど。なんか滲 み出てたんですかね。政太郎先生には前から仕事に使っていただ いたりして、演奏はさせていただいていたんですけど、ある日「僕らこういうのをやろうとしてるんだけど、君、作曲できそうだからやってごらん」みたいに話があって。あれは創邦・・・いや、別のときだったかな。
――ハッハッハ、それおもしろいなあ、どうしてそう思われたんでしょうね。
忠一郎:そうでした、そうやって突然言われたのは創邦の時じゃなかったです。政太郎先生が請け負った大きな踊りの新作のお仕事を何人もが集まって作らせてもらうときに、僕も呼ばれたんです。あれは創邦以前のことだったと思います。で、「君、ここのところを作ってごらん」みたいに言われて、もちろん手助けしていただきながらですけど、なんとか作った。それが人から課題を与えられて作った初めて。その後だったと思いますね、創邦は。
――それがある種のテストだったんでしょうね。しかし忠一郎さんの中では、邦楽の作曲はバンドで曲を作っていた時の延長だと。
忠一郎:そう、僕としては延長ですね。何においても一緒だと思いますよね、ロックも長唄も。自分のやりたいことを満たすってことですから。
――ふつう、長唄を作ろうと思うとまず楽器の制約、音の制約、唄の制約ありますけど、忠一郎さんの中ではバンドで自由に歌う感覚そのままで長唄を作っているのか、それともある種、形への快感みたいなものがあって、そこに投影しているのか、どうなんでしょう?
忠一郎:なんでしょうね・・・僕はクラシック音楽を子どもの時からさせられたみたいな経験がないので、ちゃんとした「古典」に出会ったのは長唄が最初なんです。だからかどうかわかりませんけど、もちろんこの道で行くからという気持ちがあったからですけど、長唄はちゃんと勉強しなきゃいけないと思って、やっぱり20歳前後の頃はがむしゃらにやりましたよねえ。よくやる曲はもちろんひとつひとつやっていく。珍しい曲は、音を聴いて自分で譜に起こしたりしていました。そのうちに、長唄のレパートリーが、ただの一覧じゃなくて作曲者別に分類されていきますよね、自分の頭の中で。作曲者の作る癖みたいなものもわかってくるし、それでまた、その作曲者を追っていくと、どんどん古い方へ目が向いてくる。そうすると知らない曲がいっぱい出てくる。それをまた資料とかを探してきて譜にしたりする。どうも僕は古いものへ行こうとするタイプみたいです。 思い返してみると僕は好みがはっきりしている方で、ロックをやっている時も、昔のもので「今はやり」ではないけれど、でもこれが好き、みたいなのがあったんです。たとえば白黒の映像の時代のバンドとか、ちょっとマニアックなものが好きでした。そういう性格が長唄に入ってもやっぱり現れてくるもので、これが好きって思うものがいろいろ出てきたけれども、それがまあ、今現在流行っているものと違うことが殆どなんですよねえ。
――なぜ古いものがお好きなのですかね。
忠一郎:そうですねえ。でもまあ、好みですからどうしようもないですよね。それから、長唄の世界に入ると自然とまた他のものにも出会うじゃないですか、その中から好きなものってことで、前から気になっていた地歌や河東節を習いに行ったりもしたんですよ。地歌にしても河東節にしても、いい意味で古臭いし、実際に歴史が長くてずっと今に続いていて、聴いていてもいいなあと思ったし、なにか勉強になるかなと思ったので。 しかし僕はそういう、斜に構えたというかへそ曲がりなところがあるので、曲を作るのも、人に受ける受けないとか、人からのニーズとかってあまり考えられない。自分はこれが作りたいんだっていうのを作るだけで。だから・・・古いものを好むっていうことは、現代が苦手なんですかね(苦笑い)。遠いところに逃避したいのかもしれないです。
――創邦のHPに、映画とかもマイナーなものをよく見ていたって出てましたよね。
忠一郎:マイナーなのをっていうか、あのねえ、それは映画にしろ美術にしろ狂ったように好きなものを探していた時期があったんです。僕はその当時でも既に十分古臭いロックが好きでした。でもどうしてそこに行くんだろうって思ったのが発端で、自分がなんだかわからなくなっちゃって、何が好きなのか、何がやりたいのか、自分探しの旅じゃないですけど、とにかく世の中にあるものを知って、しかも自分の好きなものを探し求めていたんです。そこで求めていたのは、時代の流れを知るとかじゃなくて、「僕は何が好きか?」ってことだったんですね。実際に気に入ったものもいくつか見つけたんですが、それは、僕が作るもののモチーフになったりというように直接的に反映するというよりは、「ものを作るときはこのぐらい掘り下げてやってもいいんだ」っていうエネルギーになるって感じですかね。世間と繋がった物差しを持っている人が羨ましいけど、でもこんなちょっと変わった人間だからこそ、人が見たことも聞いたこともないものを作ろうなんてことを思うんでしょうかね。長唄で作るなら全くのオリジナルでという気持ちは若い時からあったんです。
作品はその人の全て
忠一郎:人ってそれぞれ性格が違うから、おもしろいことをしようって人、と自分はこれですっていう人といて、作品そのものはもちろんそれぞれだし、その人の在り方とか作品づくりのやり方もそれぞれで、創邦で(同人の)そういうのを見ていると、あ、自分は自分なりでいいんだと思ったりします。ジャンルなんて関係なく、作品ってその人の全てだと思いますよね。それは創邦でやっていく中で、大発見でした。創邦をもうやめようかと思ったこともあるんですけど。演奏会を詰めてやっていたころ、しんどいなあと。でも、20年近くやってきて、これからも同人の作品を見続けたいですし、僕も、それなりにいろいろあったとしても、自分の音楽を探していかなきゃいけないと思います。
――忠一郎さんの場合、長唄の枠というか型というか、そういうの云々よりももっと個人的なレベルで創作なさっているのかしら。
忠一郎:・・・僕はわりと同じスタイルです。それはあまり変わらないというか、変えられないんですよ。いろいろ試してみる徹さんや栄吉さんみたいに柔軟ではないですから。僕は自分のオリジナルなものにこだわっています。そのためにも古いものを知りたいわけだし。古いものを知っても、その通りに作るわけじゃないですよ。それでは僕の音楽ではないです。新しいものを作るために古いものを知っておく必要があるという考え方でやっています。だから最初から一般的にはならないんですよね、僕の作っているものは。今は一般に受け入れられることはもう諦めちゃって、やりたいことをやろう、作りたいものを作ろうと思っています。
――忠一郎さんは明らかにスタイルがありますよね。それも驚くべきことに第一作の『梅若』から確立されていた。しかし周りからは忠一郎さんは古典的スタイルに見えるけど、ご自身では、作りたいものを作ったらたまたま長唄のような形になっただけなんでしょうか?とくに長唄の枠に嵌めようとしているわけではない?
忠一郎:いや、嵌めたいですね。嵌めたいんですね。逆に、型に嵌めた中で、今までのとは全然違う音楽を作りたい。
――なぜ枠に入れたいのです?ただ好きだから?
忠一郎:多分、自分がいいと思ったことに挑戦したいんです。長唄のスタイルがあり、音楽の性質、楽器の音の出方や成り行き方なんかがある中で、そこに自分の創造性をブチこんで「どう?」ってやりたいんですね。今の僕の音楽は、やっぱり長唄が基準なんです。
――てことは、長唄のスタイルである必要があるんですね?
忠一郎:そういうことなんですね。いろいろ訊いてくださって、今はっきりしましたけど(笑い)。
・・・後篇につづく