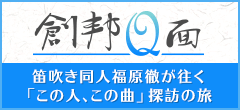第9回 創邦21公開講座「創作のキモ」レポート
今藤 政貴
歌舞伎の影響と日本人の音楽的感性と・・・
去る 5月18日、第9回の〈創作のキモ〉を開催。
今回はこれまでと少しアプローチを変え、「長唄における替手・上調子の構造」と題し、いくつかの古典曲からいろんな部分をとり出して、替手のつくられ方の発想や、音のかさなり方に対する邦楽人の感じ方や、考え方を紹介しながらキモに迫る、という趣旨。
おかげさまで、チケットは完売、こんなマニアックな企画に大勢のお客さまがお見えくださり、心より感謝!
講師は今藤政太郎、きき手には金子泰、三味線の実演は今藤長龍郎、松永忠一郎、そしてなんと太鼓!の実演に福原徹、という かつてない豪華版。
 まず、『賤機帯』の〈
まず、『賤機帯』の〈
特に『賤機帯』の羯鼓の舞の曲は、単に不協和な音の重なりが、つづくというだけではなく、
二つの旋律の調が“ぶつかる”フレーズがあって、これは聴くほうにとっても かなりの違和感だが、演奏するものにとっては違和感を越えて、ある意味難行苦行ともいえる苦痛を伴うという。
そして、音の響きの美しさが、物理法則に則ったものである以上、江戸時代の演奏者も同じように感じたはずだという。
若いころ、政太郎は、その音楽的不自然を解消すべく『賤機帯』の上調子の手を聴きよくなるように直して、少し悦に入っていたところ、師匠より「小賢しいことをするな」と叱られたそうだ。
実は、『賤機帯』の羯鼓の舞の上調子は、「娘道成寺」の〈羯鼓の合方〉の手を使っていて、手を直してしまうと、その意味がなくなってしまう。
長唄では、このように音楽的な響きの良さよりも、曲の世界観や ある種のシャレを優先して音を重ねることが、わりと常套的におこなわれているという。
このことついて、政太郎は長唄の故郷である歌舞伎の強い影響を指摘する。
なるほど、歌舞伎では、たとえば役者が舞台の真ん中で演じ、上手では竹本が語り、下手の黒御簾では、長唄が情景を描く。それぞれが、完全に整合するわけではないが、かえって それぞれの主張が伝わってくるという仕組みである。
『賤機帯』の〈羯鼓の舞の曲〉は、単に羯鼓の舞というテーマを強調するだけでなく、その不協和な重なりを巧みに利用して、狂女の心情を醸し出し、さらなる演出効果を生み出しているという点で、もう一段階上の成功作といえるのだろう。
一方で音楽家の立場からすると、歌舞伎的な重層構造の重要さを理解しながらも、複数の旋律があれば、それが美しい響きをもって奏でられるほうが良いに決まっていて、それが具現化されたものとして、今回の講座では『秋色種』の〈虫の合方〉が取り上げられた。
この〈虫の合方〉は、チンチロリンという虫の声マネの音をモチーフにし、それに〈砧〉の手や〈在郷(ざいご)〉の手を織り交ぜつつ、本手と上調子が見事な調和をみせる。
そして、なんと『賤機帯』と『秋色種』は同一の作曲の手になるものなのである。恐るべし、大名人十代目杵屋六左衛門!不協和やら調和やら、重層構造やらを、自由自在に操っていたのである。
そしてまた、それを名曲として鑑賞し楽しむ江戸の民衆。
 直には語らなかったが、政太郎の言の行間には、江戸文化の高度な成熟が、雄弁に語られる。
直には語らなかったが、政太郎の言の行間には、江戸文化の高度な成熟が、雄弁に語られる。
さて、ここまで、美しい響きが物理法則に則っていて、その感じかたは、基本的に洋の東西を問わないという前提で講義を進めてきた政太郎が、意外な指摘をする。
日本人の音の感じとり方が、やはり特殊かもしれないというのだ。
たとえば、二代目 杵屋勝三郎作曲の『船弁慶』のクドキ。そのいわばサビの部分で、三味線は唄の導入曲として、チャンチャンチャンチャン、と弾く。
この音を、我々は、愁いをおびた、美しい曲と聴くのだが・・
実はこの手では、二の糸と三の糸を同時に弾いていて、すこし単純化していうと、二の糸では、ずっとミの音を出し、三の糸はラファミファと弾いている。つまり、この短いフレーズのなかで2回も半音がぶつかり、ぶつかったまま、唄を導いている。
邦楽を聴きなれている方が多いとはいえ、受講者のみなさまに聞いても、違和感を感じるという反応はなかった。
もっとも、同じ音を、きき手の金子がキーボードで弾くと、ほとんどの人が違和感を覚えたようで、そうなると三味線という楽器の特性と関わるのだろうか?日本人は、そういうふうに楽器を発展させたのか?あるいは、邦楽を聴きなれた人間の独特の感性だという可能性も捨てきれない。
いずれにしろ、政太郎講師の、必ずしも自説にこだわらない態度と鋭い観察が、新たな研究課題を生む瞬間であった。
こうして、講座の前半では、長唄の替手づくりの基本的な発想について解説をしてきたわけだが、それでは他ジャンルではどうなっているのか、ということで、米川理事長がサプライズ登場して、〈打合せ〉と呼ばれる、“旋律重ね”の手法を紹介。たとえば、全く旋律的な相性にはこだわらずに、正月というテーマで共通する〈鳥追〉と〈神楽〉を同時に演奏したものを聞いてもらう。これも、たぶんに遊戯的な音楽であって、不協和な部分があっても、それを許容しつつ楽しむ、日本人の感性の一端を示すものとして、興味深いものであった。
 さて、休憩をはさみ、話が囃子にまで広がる。
さて、休憩をはさみ、話が囃子にまで広がる。
長唄の曲の成り立ちに、歌舞伎的な重層構造の影響をみるのであれば、お囃子の存在を無視するわけにはいかないというわけで、『越後獅子』の太鼓地と、『五郎』の二上り「藪の鶯~」の部分が俎上に。
『越後獅子』の太鼓地は、角兵衛獅子を舞う場面に当たる。そこで、神楽獅子風の音階の替手が入り、獅子舞の雰囲気を作り上げるのだが、ここにもう一つ仕掛けがある。太鼓が、能楽の『石橋』の獅子で使われる手を打つのである。まさにシャレた獅子尽くしであって、「牡丹は持たねど、越後の獅子は~」という歌詞ともぴったりくる。
『五郎』の二上り「藪の鶯~」はどうか。
この部分は、唄と三味線だけを聴けば、しっとりとした曲調なのだが、〈アバレ〉や〈岩戸〉などの囃子の手が入ることによって、まさに"曽我五郎時致”の荒事の世界が作り出されている。いわば、曲の内容の本質的な部分を囃子が担っているわけだ。
このように囃子は、多くの曲で、内容の本質部分を立体的に補強しており、替手以上に、替手らしい仕事をすることも しばしばなのだ。
そして、創作する者に限らず、演奏に携わる者も、こうした曲づくりの構造をしっかリ理解したうえで、それに臨まなければならない、として、講座は結びとなった。
今回の講座では、歌舞伎的な重層構造の影響という視点から、古典邦楽の音の重ね方の観察と分析を通して、創作のキモを探った。
手前味噌ながら、創作のヒントというにとどまらず、演奏のあり方や、鑑賞のヒントをも提示できたのではないだろうか。
さてここで、筆者の感想を少し。
三味線の本手と替手の関係は、時代が下るにつれて、音の響きの美しさや、整合性が優先されつつあるようにおもう。また、囃子に関しても、リズム楽器としての重要性がより増しているように思える。それらが絡みあえば、音楽は以前よりも複雑にもなる。
もちろんこのことは、より美しい、あるいは よりおもしろい音楽が志向された結果であって、ある意味 自然な流れである。
こうした時代の潮流のなか、古典的な重層構造を作品のなかで成立させていくのは、決してやさしい仕事ではないだろう。
そんな今、各個がどういう方向を向いて創作に挑むのか、創作者一人一人の大きな課題となるのではないか。
また、このテーマは、邦楽とは何かを考える上で、ひとつの重要な鍵となるのではないか。