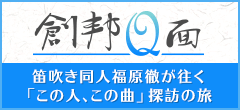第5回 創邦21公開講座「創作のキモ」レポート
金子 泰
毎回2曲ほど取り上げ、創作者の視点で解剖しその曲の「キモ」に迫るこの講座、今回は「“洋素材”で創る—普遍をもとめて」と題し、同人の作品である福原徹作曲「キリエ」と杵屋巳太郎作曲「ほら男爵の大冒険」(ビュルガー作、竹柴潤一脚色)を、それぞれの作曲者に解説願った。
両曲とも、手前味噌ながら発表時に好評いただいた作品で、今年11月5日に開催予定の「第13回作品演奏会」で再演することが決まっている。
第一部は、講師・福原徹、ききて・今藤政貴で福原徹作曲「キリエ」。
2002年6月「創邦21第3回作品演奏会」にて、笛・福原徹、唄・今藤政貴で初演。
“キリエ”とはラテン語のミサ典礼文、要するにミサ曲の頭の歌詞。全曲通しても歌詞は「キリエ エレイソン(主よ 憐みたまえ)/クリステ エレイソン(キリストよ 憐みたまえ)」のみ。曲は3章立てになっており、まず章ごとに区切りながら曲を聴く。音源は2003年NHKFM放送のためのスタジオ録音。演奏は初演と同じく徹と政貴。つまり目の前の2名による演奏。
㈵章を聴いた後、核心に入る。すなわち、なぜ“キリエ”か?
徹「別にキリスト教を信仰しているわけではないが、バッハが好きで(バッハのCDが500枚くらいある、と言った)「ロ短調ミサ」もよく聴いていたことも関係あったかもしれない。創邦の同人は三味線弾きが多く、彼等は長唄的な、編成の比較的大きな作品を創り、逆に僕は第一回、二回と笛のソロの曲を創っていた。三回目の演奏会は自分のリサイタルの後で、それに向けて準備を進める中で何か今までとは変わったことをしたいと考えた。笛と唄だけの曲を創りたいと考えた。そのとき政貴さんがいた。政貴さんとは創邦の中でよく知るようになって、ひとり超然としているようなたたずまいがどう見ても“キリエ”だろう、となった。」
つまり徹の笛と政貴の唄のための曲なのだ。しかし作曲し発表するにはいささか躊躇もあったという。
笛と唄という特異な編成。キリスト教の典礼文という題材。「それでも、やりたいならやっていいんじゃないか。そもそも子どもの時合唱団にいたこともあって、このことばが自然にもう“在った”。」
抑制の効いた、しかし自然なメロディーの㈵章、篠笛を能管に持ち替えて不安定な音程に緊張の高まる㈼章、㈽章は再び篠笛と唄で、最後は少し光が見えるように終わる。
今回この講座で徹の「キリエ」を採り上げるにあたって付けられたサブタイトルは「出会い、そして転機…」である。出会いというのは、創邦で政貴に出会ったことも含めた、この曲の成立要素との出会い、あるいはこの曲自身との出会いか。では転機とは?
自分が作曲をするのは「笛だけの曲というのはもともとない。師匠(寶山左衛門師)が作り始めたと言っても過言ではないくらい。いきおい、自分が気持ちよく吹ける曲は自分で作るしかない。今でも演奏の延長で作曲をしている。」という現実的な話をしたうえで、
徹「『キリエ』のような曲はどうなのかなと自分で不安だった。自然に音楽をやりたいと思っているというだけの、いわば曖昧な気持ちでこんな大事なことばを曲にしてもいいものか、人は受け入れてくれるのだろうか、と。ところが創邦の演奏会で発表してみると、たいへん好意的に受け入れられた。そのとき、やりたい編成やテーマがあったらやっていいんだと思った。この曲以降、自分のリサイタルにしても、やりたいことは構わずやろうという姿勢で臨んでいる。僕にとって大きな転機となった曲です。」
「キリエ」は2002年に創邦で初演され、翌2003年にNHKFMで録音・放送、2004年の福原徹リサイタル(於紀尾井ホール)で三演された。そのリサイタルでのライブ録音で全曲を最後に聴いた。ホールの響きや演奏の伸びやかさは、たしかに先ほどのNHKの録音よりも奥行や広がりを感じさせた。今度の11月は残響のほとんどない紀尾井小ホールでの演奏である。また別の趣が出てくるのだろうか。楽しみである。
休憩を挟み、第二部は杵屋巳太郎が自作の「ほら男爵の大冒険」を取り上げる。
昨年10月の創邦第12回作品演奏会で発表され、ほら男爵役の杵屋巳津也氏の熱演もあって好評を博した。
巳太郎が「皆さんに楽しんでもらえるようにと思って作曲した」と言うこの曲、原作はドイツのビュルガー、竹柴潤一氏の脚色。登場人物はほら男爵と奥方。男爵が居間で奥方に冒険譚を語って聞かせるという体(奥方役は柏里文氏)。
そして巳太郎がこの作品で目指したのは、「擬音、擬態を三味線で表現すること」。鉄砲、大砲、時計の音、転んだ様子、馬が高い塔のてっぺんの十字架にぶら下がってぶらぶらしている様子、風が吹く様子…それらを全部、三味線の音で写実に表現しようという企てであるという。
巳太郎の中に、展開する作品の絵が芝居のしつらえのようにきちんと描かれているのだろう。たとえば前奏・後奏でもある時計の音を模した部分は、ボーン、ボーンと時を告げる音が歪んで響き、そこに秒針を写した三味線の音が重なるのだが、「ダリの絵のように、歪んでぐにゃりとなった時計」(巳太郎)を表していて、室内であることを示すばかりでなく、年齢不詳の男爵やこれから始まる話の非日常性というか“アヤしさ”までも醸し出す。「写実に表現するよう作った」と巳太郎は言うが、しかし風の音、雪の音、時計の音にしても巳太郎というフィルターを通して出てきた音であるから面白いのだし、こうして解剖してもらう甲斐もあるのだ。
この曲も3章立てで、最初の話ではほら男爵は厳寒のロシアを旅するのだが、冬の描き方にしても、巳太郎は「日本の冬はこんなかんじ」と「四季山姥」の冬のくだりを弾き唄い、しかしロシアですから風も雪も日本と違って酷いんです、と言って独自のロシアの冬の描写をする。まさに「三味線で表現できることに挑む」ために、三味線音楽的に未開の洋素材で創作したのではないかと思われた。
さらに、旅の手—道中の手である「弥次喜多の手」、「綱館」にもある「“ジャンプ”の手」のような古典の手も入れ、カモが脂の多いベーコンを飲んではつるり飲んではつるりと出して全部繋がってしまうところでは俗曲の欣来
きんらい
節を採った「ラップ調」(※)、そのカモが一斉に飛び立ったはばたきの手(?)はラルク・アン・シエルに触発されたもの、と、洋の東西・時代の今昔また多ジャンルを自由に往来しつつ、全ての部分に「ここはこれを表している」という明確な意図、明確な表現対象があるのは、この曲の大きな特徴である。
作品全体としては、ミュージカルのような、オペレッタ、オペラ・ブッファのような仕上がりを狙ったという。たしかに。巳太郎も言うとおり、この作品は演者(演奏者、ではなく)の演技あってのもの。このあいだの演奏会の録音を聴いたのだが、音だけではわからない部分が多々あり、映像つきだったらどんなによかったか。その点は残念だった。今回見えた方々には、もちろんそうでない方々にもだが11月の上演を是非見ていただきたいと思う。
“洋素材”で創った今回の二曲、それぞれ曲の雰囲気も性格も違うのに、また“洋素材”とひとくくりにしてしまっているが典礼文の「キリエ」と18世紀ドイツのビュルガーの「ほら男爵」とでは全然違う質のものなのに、二人の作曲者の話を聞いていると、根本的なところで何か共通する思いがあるように感じられた。つまり、作曲者たちは二人とも、洋と和の融合とか邦楽の新たな展開とかいうような大上段に振りかぶった、いささか理念的でもある志を以ってそれぞれの題材を選んだのではなく、ただ自らの音楽的欲求のままにその題材を採り上げたようであった。そしてそれゆえに、理念先行ではないゆえに、地に足の着いた作品になり得たのではないかと思う。
質疑応答にはなかなか手が挙がらず、かく言う私もそのときはボーッとしていて、後で「巳太郎さんにキンライ節とラップの話をもう少しよく聞いておけばよかった」と悔やまれたりもしたのだが、ともあれ11月の演奏会には、「キリエ」も「ほら男爵の大冒険」もライブでじっくり聴かせていただこう。
(※)欣来節は明治時代に流行したはやり唄で、長唄「雨の四季」の飴売りの口上のくだりに使われているとのこと。そこの部分の実演もあった。巳太郎曰く「ラップとチョボクレ、欣来節は繋がっている気がする」。