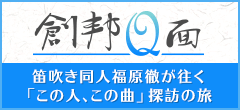第16回 創邦21公開講座「創作のキモ」レポート
シリーズ 名曲を聴く③
「紀文大尽」(明治44年)
作詞/中内蝶二
作曲/四世吉住小三郎(慈恭)、三世杵屋六四郎(二世稀音家浄観)
~邦楽の近代の在り処を探る〜
今藤 政貴
 1月9日に、第16回目の創作のキモが開催された。
1月9日に、第16回目の創作のキモが開催された。
今回は「シリーズ名曲を聴く」の3回目で、配川美加先生(以下、敬称略とさせていただきます)をゲストにお迎えし、今藤政太郎同人とのいわばダブル解説で、長唄研精会の傑作「紀文大尽」(四世吉住小三郎(慈恭)、三世稀音家六四郎(浄観)の合作)を取り上げた。
話は盛りだくさんだったが、その中でも印象に残ったことを紹介しようと思う。
講座は、長唄研精会の話から始まる。
近代化が志向される明治時代の後期、歌舞伎から独立した場所で四世吉住小三郎(慈恭)、三世稀音家六四郎(浄観)によって研精会は創始される。その後、多くの文化人が支持し、演奏団体、そして創作団体として近代長唄を牽引し、一世を風靡していく。
政太郎は、長唄界の主流派としてはスタートしていない研精会の、自らの芸と志を信じ、批判を恐れず伝統と革新の間を行き来した姿にシンパシーを持つようだ。
その姿は研精会の音楽的特徴からも仄見え、たとえば慈恭の大胆に語りを取り入れた唄は、唄い方革命をもたらしたであろうし、一方で、基本的にオフビートで弾く三味線やあまり見栄えのしない小さなバチは、そのルーツこそ詳らかではないものの、おそらく伝統的なものであって、良いものは良いという合理性のあらわれではないかという。
さて、いよいよ「紀文大尽」である。
ここではまず中内蝶二の作詞の秀逸さが取り上げられる。
歌詞は全六段から成っており、初代紀国屋文左衛門(紀文)の冒険的成功譚(五段まで)に始まるが、実はそれが二代目紀文の夢であって、ここから(六段から)が本題となる構成の妙。
そこには二代目ゆえの苦悩 〜親の得た有り余る財に商才を奪われ、その代償に、粋にもまれた洗練とそれゆえの脆弱さを得たかのようにも思える「蒼白きインテリ(政太郎の言による)」の苦悩〜 が行間に描かれる。
その屈折した人間描写は、近代の匂いにあふれ、それでいて終盤は大尽舞で華やかに収束するバランス感もさすがで、まさに近代長唄にふさわしい本が出来上がったということなのだろう。
さあ、その詞を両作曲者が名曲に仕立てあげる。
浄観と慈恭とが交互に段ごとの作曲をしたそうだが、それぞれの個性はあれども違和感のない繋がりは、演奏にとどまらぬ稀代の名コンビぶりのあらわれだ。
 そしてこの作曲のなかにも伝統を引き継ぐ姿勢と、革新的な工夫とがはっきりと見てとれる。
そしてこの作曲のなかにも伝統を引き継ぐ姿勢と、革新的な工夫とがはっきりと見てとれる。
まず、三味線の手や唄のフシについては、常套的な音の積み重ねのなかに、先行作品の手の引用が随所に見られる。
これは、配川の丹念な研究が示唆するように、無意味な転用ではなく、たとえば傾城の誠云々のくだりに『傾城(十代目六左衛門作曲)』の一節を、八万五千籠を八百五十万輛の車に載せるくだりには『三日月雷女太夫』の「鴨が八百羽〜」の一節を使うなど、わかる人にはわかるシャレた引用であって、伝統的な作曲技法を踏まえたものである。
さらに、一般的な意味を帯びた、決まった手(フレーズ)を曲中に使うことも常套手段なのだが、政太郎が指摘するのは、その置き場所や組合せの巧みさと斬新さである。
たとえば第六段に見られる「雪の合方」のセリフ地的な使い方は、唄と語りを自在に操る研精会の芸によるものだという。
また、上でも少し触れたが、この本のキモの一つである第五段から第六段の、夢から現実への転換の場面の作曲も絶妙だという。
第五段はみかんの運搬の活気ある場面で、その終盤にサワギの手からスガガキの手を使って次の段の吉原の場面を誘導しているのだが、こういう手の繋がりから想起されるのは、普通、華やかな吉原の景色であったり豪興であったりの場面、音楽であろう。しかし実際にそこで聴こえるのは、零落を予感させる、吉原の一間を描くしんなりした曲である。期待を上手く裏切ることで、夢と現実の落差を浮き彫りにするという仕組みだ。
さらに遡ると、第四段から第五段では本調子から三を下げていることも特筆すべきことで、政太郎は「こうしたときは普通、二を上げて曲に活気をつけたいところなのに、あえて三下りにしたのは、サワギから三の糸を上げてスガガキにする構想だったのだろう。しかも三を下げる音を聴かせずに、一の解放絃から始めるアイデアしかり、三を下げているにも拘わらず場面にふさわしい活気のある音を作り出していることしかり、まさに非凡」と述べる。
ちなみに浄観は、六段目の導入の音付けにも、非常に悩んだという。
それは、この場面の重要性を意識していたことの証だろうし、その成功が"革新的な”名曲を産んだ一大要因なのだろう。
革新といえばもう一つ、斬新な手法として忘れてはならないのは、やはり前弾きだろう。
政太郎によれば、アタマの一下りのドドーンだけで嵐の海が表現されており、それに続く嵐の激しさを表す手順の出来栄えの良さはもちろんのこと、それ以上にツレ弾きにしたことが効果を倍増しているという。
そして政太郎は、この時代に唐草のような手を曲のド頭に配置して、なおかつそれをツレ弾きにするという発想は、当時の常識を突き抜けていて、浄観としても会心の作曲だったのではないかと見ている。もしかすると、少なくとも第一段から第五段までの成功は、この前弾きのできた時点で約束されていたのかもしれない。
なお、本来ツレ弾きのこの部分を「しんどい」と言いながら、同人の今藤長龍郎が独奏であざやかに実演していたことは、もしかすると当然なのかもしれないが、やはり大したことだと思う。これは創邦21の手前味噌。
 と、ここまで印象に残った話を羅列してきたが、歌詞が成功し、曲の導入に成功し、最も大事な場面転換にも成功し、曲の収束にも成功しているのが『紀文大尽』であったことが得心できたように思う。
と、ここまで印象に残った話を羅列してきたが、歌詞が成功し、曲の導入に成功し、最も大事な場面転換にも成功し、曲の収束にも成功しているのが『紀文大尽』であったことが得心できたように思う。
そして時代の要請に応えた傑作となった所以を、その深淵には及ばずとも、筆者なりにその一端をかじりとれたような気がしたのである。
追記 当代の吉住小三郎さんと稀音家六四郎さんにはお話を聞かせていただき、さらに小三郎さんからは音源のご提供をいただきました。
創邦21の一員として、厚く御礼を申し上げます。
(2024年1月9日 於 アコスタディオ)