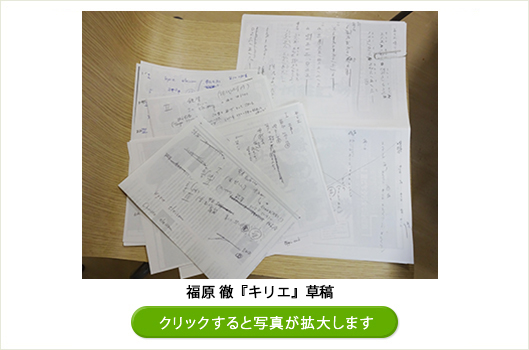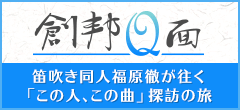笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月は本郷の東大学食で金子 泰と語る
金子泰/福原徹篇
確証と確信 [後篇]
音楽とともに
金子:徹さんは創邦には文字兵衛さんに誘われたとおっしゃいましたよね?
徹:そう。最初は文字兵衛さんからよかったら参加しない?って言われた。ちょうど97年にぼくが自家版でCDを作ったんですよ。CD作ってすぐぐらいの時にお話しがあった。
金子:CDはその後も作られて、今3枚ですか。
徹:3枚出しました。今ちょっとストップしてますけど。でも自分自身はまったく作曲には興味がなかったんですよ。子供のときから唄うことが好きで、音楽が好きで。虚弱っていうんじゃないけど、ひとりでずっと部屋に閉じこもってひたすらレゴで遊んでいる子だったのね。あとは、歌うことはとっても好きで、当時母親が長唄をやっていましたから、ちょっとそれを聴きおぼえで唄ってみたりとか、上手かったわけじゃないんだけど好きだったんですね。
小学校に入ったら音楽の先生が非常に熱心な方で、NHKの児童合唱団に送り込んでいたのね。で、僕もNHKの合唱団に入って歌ってたんですね、長唄は地声で唄って、合唱団に行くとボーイソプラノで裏声で歌って、子供だから全然違和感がない。使い分けてる気すらない。どっちも好きだった。それが変声で突然高い声が出なくなっちゃって、だからそれで終わり。中学、高校に入って何か悶々としていたんだけど、やっぱり音楽がやりたかったんでしょうね、声は出なくなっちゃったから何か楽器をしたい。で、なぜか笛をやりたくなった。これは自分でも気が付かなかったんだけど、笛ってすごく高い音だから、高い声をやっぱり出したかったんじゃないかと、自分が出なくなった高い声を出す代わりに笛に行ったのではないかと、後から人に言われましたけどね。
金子:なるほど。なんか説明つきますね。
徹:じゃあ誰に習おうかってなって。当時僕が聞いていた伊十郎全集のレコードは、ほとんど福原百之助っていう人が吹いていたわけ。で、いいなあとなって、母親から伊十郎先生のご家族に頼んで、その伝手で紹介してもらってね。それがまたおかしくって、当時うちの先生はすごく忙しかったから最初はそんなつもりじゃなかったんだけど、手ほどきが肝心だなんて言われて突然、じゃあ僕が見てあげましょうってことになったんです。だから僕は初めから、つまり持ち方とかそういうところから寶先生なんですよ。で、高2の6月に始めて、先生のそれこそ赤坂と新橋の芸者さんのお稽古の合間にお弟子たちは1か月に1回見てもらう感じでしたから、僕も初めての稽古って、赤坂の見番に行って芸者さんたちが大勢いる中でだったの。そうしたらどういう拍子か一発で音が出ちゃって、チヤホヤされるし舞いあがるし、先生には「接吻にいい口だね」なんてからかわれたりしてね(笑い)。
その年の11月に国立劇場でおさらい会があって、もちろん出るつもりもなかったのだけど、なんかね、お弟子さん同士で「君は何やる?」なんて訊かれて、僕は「やるんだったら高尾さんげ―もみぢ葉をやりたい」と言った。で、先生も、ああいいじゃないってことになって、母親に唄ってもらって、お三味線はプロの先生に頼んで、ぼくは『もみぢ葉』を吹いたんです。始めて5か月、ということは始めてお稽古5回です。
金子:吹けちゃうものですかね。
徹:いや吹けてやしないですよ。でもこの「国立劇場に出た」っていうのが自分のターニングポイントになったと思っています。というのはね、久々に、自分が舞台でパフォーマンスしたわけですよ、国立劇場という大きな舞台で、プロの人を従えてね。すごく大変だったしあがったし緊張してヘロヘロだったんだけど、ひさびさに自分の居場所のようなものを感じたんですよね。で、こっちでもたいへんなことがたくさんあるだろうけれども、それは頑張ってみてもいいなあと思った。あとはこのあいだ政太郎さんに訊かれてお話した通りです(注:政太郎篇番外篇)。
金子:で、芸大にお入りになった。
徹:芸大には入れたんですけど、入ってからがたいへんでしたよ。なにしろ経験が浅くてレパートリーがないから、一所懸命やった。楽しかったですよ。でもほんとうに、作るっていうのはその当時全然考えたことなかった。子どもの頃、指揮者になりたいと思ったことはありますよ。カラヤンが大好きだった。だけど作曲家になりたいとは思わなかった。当時すでにバッハが好きだったんだけど・・・。
金子:バッハはいつ頃からお好きになったんですか?
徹:僕がバッハを意識しだしたのは非常に不純でね、合唱団の先輩たちがなにかの番組で『G線上のアリア』を歌ったのをね。スキャットみたいなそんなのだったと思うんですけど、それを聴いたときにすごく素敵な曲だと思って、それからバッハバッハってなった。でもそんなに児童合唱ではバッハを歌うチャンスってないんですよ。教会の聖歌隊ではないから。
作曲をはじめる
徹:学校の中で作曲の機会はあったんですけど、そういうのはどっちかっていうと逃げ腰だったし。文字兵衛さんなんかは当時から挑戦的にバリバリやってたけれども。その文字兵衛さんの影響もあって、即興とかはやっていたんですよ。同級生だから、文字兵衛さんとか、お能の小早川修さんとかと。そこに洋楽の人とかも捕まえて、即興と「称する」ってかんじですけど、芸大の部屋を借りていつ終わるとも知れない音楽をセッションするだとか、そういうのに面白おかしく参加はしていました。
金子:作曲の第一作は卒業なさってからですか。
徹:えっと、学校の中で作曲発表があるので、それで作った曲ですね。三年のときに『秋やがて冬』って曲を作って、あたりまえだろって感じですけど(笑い)、笛2管と三味線1丁。笛は徹彦さんが当時別科にいらしたので、徹彦さんと。三味線を文字兵衛さんに弾いてもらって、やりました。
金子:ではどうして作曲をなさるようになったのです?
徹:寶先生が作曲なさるから。先生が花柳茂香先生と一緒に新作をよく作られていたのだけど、その作り方がちょっとおもしろくて。ふつう、曲ができてから振りがつくじゃない?それがね、ある程度振りができているわけですよ。
金子:最初に?
徹:そう。で、そこにポッと充てていくかんじ。ある程度一緒に作る感じ。並行してというかね。それをちょうど僕がお供している頃にそういうのがあって、それが見ていてとっても面白かったんですね。で、先生が踊りの振りを覚えていなきゃいけないので、ビデオカメラを持って行ってそれで撮ってコピーを先生に渡して、そんなことを自発的にしたりもしていたんですね。それがとても楽しかった。作る現場にいることがね。それでしかも先生方が喋っていることが、ある種、禅問答のようなかんじで、譜面を見てここがああでこうでっていうのじゃないわけです。「寶先生、ここを広くしていただいて」っていうような言い方をなさる。
一方で当時毎年、うちのお弟子さんの発表会を、お吹き初めと称して毎年1月にホールでしていたんですよ。最初、僕は袖で幕の開け閉めとかをしていたんですけど、ある時ふと、ぼくにとってお弟子さんと対等にやることは何だろうと考えた。それで、じゃあ曲を発表するようにしようと思ったわけです。で、文字兵衛さんが笛がお好きでうちに習いに来ていたときに、お吹き初めに文字兵衛さんもせっかくだから出て吹いてもらい、ついでに弾いてもらって発表したのが、『三づくし』。
金子:その曲は創邦の試演会で録音で聴きました。なにしろ3を集めた曲でしたね。
徹:全然アイディアは浮かばなかったんですけど、とにかく春夏秋冬みたいなのはやりたくなかった。それから意味深な題名をつけるのも嫌だったので。三味線か、3だなっていうのが最初。そのあと、『一枚の写真』と言うのを作ったら1と3ができたので、面白がって「ふたり」「四人の男」を作って「五人囃子」を作って、1から5までできたところでちょうど97年、CDを作ろうと思って6から10を作り足して作ったCDを文字兵衛さんが創邦の集まりで紹介して、それで創邦に入れていただいたんです。
金子:それぞれの曲の発想がなんとも、自由といいますか。
徹:いろいろやって、いろいろ聴いていたからですかね。バッハも見つけて聴いていたり。
金子:じゃあ、レンブラントはいつからお好きなんですか?徹さんといえばバッハとレンブラントですが、レンブラントの絵を題材にして曲も作ってらっしゃいますよね。
徹:僕は美術は全然興味がなかったんです。決定的なのは、絵って見ないと見えないでしょ?音楽はよそ見していても入ってくるでしょう。だから絵って何か遠いもののような、僕には関係のないものの気がしていたんですね。ところが寶先生は日本画がお好きで、合間があるとけっこう絵を見にいらしていた。その影響で僕も一丁前に絵っていいもんだななんて思いだしたんですね。そんなときに、82年。生まれて初めて自分でお金を払って、ブリヂストン美術館のエルミタージュ展に行って、もんのすごい衝撃を受けて、はじめて絵をこのまま欲しいと思った。それから今も追っかけています。でもね、手前みそではあるけどひとりの画家を追いかけるのはメリットがあって、つまり定点観測とでもいうんですかね、自分が変わったのがわかりますよ。
金子:徹さんはご自分が演奏するためにお作りになるわけですよね。
徹:そうね、僕の場合は、自分で吹きたいものを作るっていう意味合いが大きいですね。だから作曲家というよりはシンガーソングライターという感じですね。実際、古典の曲だと笛メインのものは殆んどないし、だからそれを平たい意味で作曲と言っていいのかわからないんですけどね。作曲といっても、笛の場合はたぶんに演奏に即興的な要素があって、土台みたいなかんじのところがあるのかもしれない。
とにかく今思っているのは、なるべく自分に制限をかけずに、おかしくてもいいからやりたいようにやるということ。こういうのをやるとおかしいんじゃないかとか、それはないんじゃないかとか思うと、却ってうまくいかないんですよね。だからやれるところまでやっちゃうのがいいんじゃないかと思うんです。でもなかなか最後まで引っ張っていく力が難しいですね。自分で今まで作ってきたものを見ると、モチベーションの大きさがやっぱりものすごく曲に反映されています。言葉の力とか、強烈なモチベーションがあった曲は再演していますね。
『キリエ』の場合はあの当時の世相(注:いわゆる9.11の頃)があって、あの言葉を叫びたい気持ちがあった。自分が今できることって何だろう、何もできない、ただ「憐みたまえ」しか思いつかなかった、それは素直な感情だったんですね。『草の祈り』だったら詩のパワーですね。テーマが非常にはっきりしていました。
自分に最後まで引っ張る力がないから、思いつきがあってもいい曲にはならないですね。僕の場合はそれのみで引っ張るっていうかんじですので、ひたすら心の中の叫びみたいなものにすがっていくしかないんですね。で、それがクリアにならないと、だめなんです。なかなか進めないし、進んだとしてもなかなかしっくりくるものにならない。
でもね、レンブラントの絵を見たりするのってほんとうにいいモチベーションになって、つまり、・・・感動するんですよね。すごいことをやってる人がいたんだなあ。すごい作品を描いているし、何百年もたって、全然ちがう国の一介の、絵描きでもない笛吹きが見てびっくりして、オランダまで追っかけて見に行かせるような、そんな酔狂なことをさせるような何かがあるわけじゃない?で、神様じゃなくて実際の生身の人が描いたわけだから、そこがすごいと思うんですよ。ということはね、同じようにはできないかもしれないけど、できないって決めるのはたいへんおこがましいのではないかと思うんですね。やっぱり、やりたいのだったらやるしかないんじゃないかな、とね。
だって、音楽って救いでしょう。こんなこというと青臭いんだけど、でもことばを超えてダイレクトにくるものでしょう?長い時間かけて意外と効いてくるんじゃないかと思うんです。
金子:徹さんはこのところ毎年リサイタルをなさっていますけれど、選曲の基準みたいなものはありますか?常に新しいものは入れようと思ってらっしゃるわけでしょう?
徹:先の事はわからないですけど、最初のリサイタルをするときに、寶先生の会を参考にさせていただいたんですよ。先生はご自分の会を古典2曲にご自分の新曲1曲というパターンでなさっていたのでね。古典っていうのは、長唄だったり清元だったりってことです。
僕は、40歳になったときに自分の会をやろうと思い立ったんですが、どういうリサイタルにしようかと思ったとき、当時僕は既に拙いけど少し曲を作っていた。一方で、ふつうの邦楽に使っていたホールがどんどん閉鎖されて、逆にコンサートホールが増えてきていた。みんなが言うにはコンサートホールは邦楽には向かないと。緞帳がないし、山台がない、屏風がない、それから音が響きすぎる。だからできないと。でもほんとうにそれでいいのかなあって思ったわけです。できないって言っていたらどこでもできなくなっちゃう。コンサートホールでやる人もいるにはいたけど、いつもやっていることを、そこでやろうとする。そうすると響きはたしかにぐちゃぐちゃになるわけで、使いにくい、弾きにくい、見てる方も辛いとなる。
それから、歌舞伎の流れから来ているのだと思うけれども、たとえば桜の立ち木を出すとか照明を使うとか、演劇的、視覚的演出に走るきらいがある。それはぼくも嫌いじゃないけど、風情を出したいのだったら池のあるところや森の中でやればいいと思っていたんです。実際そういう機会があったからですがね。
それで逆に考えて、コンサートホールでできるような演奏形態に曲を作ればいいんじゃないかって思ったわけですよ。でね、幾つかのホールを見たときに、津田ホールがいろんな点でよかったので、そこで第1回をやったんです。プログラムも先生と逆にして、新作3曲に古典を1曲。古典を義太夫の『関寺小町』にして、竹本駒之助先生と鶴澤津賀寿さんに出ていただいた。そのときは1曲目に新作で笛のソロ。2曲めは笛の二重奏を自分で作って寶先生に出ていただいて、3番目に古典の『関寺』をやって、4番目は、大鼓ふたり、鼓ふたり、笛3人っていう変な編成の曲を作ってやったんです。笛っていう楽器が、そういうホールでもなんとかやれるものだからだというのもあります。自分は演出は好きなんだけども、演出をしないのをやりたかった。やっぱりクラシック音楽がすごいのは、なんにも演出的な背景がなくて音楽だけで聴かせるでしょう。音だけで成り立つ。それを一度やってみなきゃいけないんじゃないかなと思って。それと自分が昔合唱をやっていて、そういうホールに特にアレルギーもなかったし、違和感がなかった。でも洋楽のホールでやるから洋服にしなきゃいけないってわけでもないと思ったし、黒紋付で出てきて立って吹くと。まあ自由にやりたかったというのもあったんでしょうね。
それと、洋楽的なものを作りたいと思ったわけではないんですよ。寶先生の曲みたいなのを作りたいと思ったし、長唄のメロディみたいなのを作りたいと思ったし。そこと途切れているわけではなくて、繋がっていて、でもこういう場所でできるようなのをやりたいと。それが企画としても珍しいものだったからか、評価をいただいたわけですけれどね。まさかでしたけど。それよりも、空間と曲が合っているもの、自分が作りたいものを作ったわけです。
金子:リサイタルで曲を作るのと創邦で曲をつくるのと、どこか違いますか?
徹:場所が違うのは曲作りにもある程度反映されますよね。それから、僕は創邦ではあまり大きい曲を出そうとは思っていないんです。
金子:たしかに編成にしても曲自体も小さいものをお出しになっていますよね。
徹:そう。ひとつは他の人たちが三味線の曲を出してくるから、ぼくは三味線を使おうとは思わないし、だいたい大きい編成になりがちな中で自分は大きくない方がいいだろうなっていうのがありますしね。
金子:だいたいその・・・この「11面相」でもね、毎回といっていいくらい「弾き唄いはしませんか」「ミニマムな編成の曲はどうですか」って訊かれているでしょう?ミニマムな編成の曲に拘っていらっしゃるように思うのですが。
徹:そう、たしかに。というのは、邦楽の良さはそこにあると思うんです。
長唄にしても、大勢でやる曲だってユニゾンじゃない?まあ替手があるぐらいですよね。7丁7枚でやっても7声ってわけではない。大和楽とかはさておき邦楽は単声なんです。つまり1丁1枚で成り立つわけですよ。ぼくはそこから始めた方がいいんじゃないかと思っていて、最初から大編成の曲を作るのじゃなくて、小編成から始めて足りなかったら足してゆくと。特に邦楽の場合は楽器の音色とか余韻にかなり含みがあると思うので、そこを使わない手はないんじゃないかと思うんですよね。数を増やすとどんどんそれが薄れていくでしょう?
もちろん音色や余韻に頼り過ぎてはいけないとも思います。でも、音の重ね方で工夫していこうとなると、邦楽器の良さが減っていっちゃうんじゃないかなあ。ミニマムにした方が自分に忠実にできるような気がしますね。
たとえば『六段』みたいな曲、めりやすの『明の鐘』や『黒髪』みたいな曲が作れたらいいと思う。そういう曲は、時代的に難しいし、まあできないんだけど、「いいものができないから作らない」は違うんじゃないかなと思いますね。みっともなくていいと思う。お客さんには失礼な話ですけれども。要は可能性を拡げるということです。他で聴けないものというか、こういうものもできますよっていうのが、創邦から出てきてもいいんじゃないかなあ。
金子:創邦21同人の私たち自身が、自分たちの作品演奏会をどう位置付けるかということですね。自分の中で間違いない安心安全なものを出して定評を得ようとするのか、勇み足覚悟でひとつやってみるのか。自分ではかなり挑戦的なことをしたつもりでも全然普通だったってことも、ままありますけど。
徹:もちろん本人が作りたいものを作るべきなんですけど、僕がちょっと聴いてみたいので、いつも誰に対してもそういう質問を僭越ながらしているわけですけど、なんかね、小編成の方が個性が浮き出る気がしますよ。編成を増やせば増やすほど、本人たちが思うほどには違いはわからなくなって、外から見たら「ああ、邦楽の会ね」ってことになっちゃうんじゃないかな。それじゃ残念なんでね。
おそれない
 徹:僕は自分が作る方のタイプだとは思っていないところがあって、音楽は好きだったんだけど作曲は思いもしなかった。だから未だに自分で半信半疑なところがあるんですよね。やるしかないとはいっても、作りたいものがパッと作れるかというとそうではなくて、実際どういうものを作りたいかっていうと、自分でもよくわからない。
徹:僕は自分が作る方のタイプだとは思っていないところがあって、音楽は好きだったんだけど作曲は思いもしなかった。だから未だに自分で半信半疑なところがあるんですよね。やるしかないとはいっても、作りたいものがパッと作れるかというとそうではなくて、実際どういうものを作りたいかっていうと、自分でもよくわからない。
インタビューしてきて、みんな自分の場所で大なり小なり暗中模索していて、それがたまたま上手くいくときもあればそうじゃないときもあって試行錯誤しているのがわかって、それは僕にとっては心強かったし、それで自分もいいんだなって思いましたね。それぞれの立場でそういうことをやる仲間がいる。それが心強いと思うんですね。いい悪い、優劣じゃなくて模索し続けているのが大事だと思うんですよ。結論がない世界じゃないですか。どれがいい作品かは後になってみないとわからないし、本人がいいと思っているのがいいと思われるとは限らない。時代によって評価も変わるし。でも、作りたいと思ってらっしゃる方はほかにもたくさんいらっしゃると思うけれど、ここの10人が、それぞれ年代も違うしジャンルも違うし、生い立ちというかこの世界に来た経路、作る作品もそれぞれ違うんだけれども、でもみんな何かを作りたいと思ってここに集まっているっていうのがいいなあと、改めて思いました。
僕は、邦楽の人って曲を作らなきゃいけないと思っていたんです。今までの邦楽の曲は全部演奏家が作っていて、今みんな過去の演奏家がつくった曲を有難がって演奏しているけれども、もしそれが有難いのであれば、作り続けなきゃいけないんじゃないか。だって先輩のやった仕事の「おこぼれ」だけじゃ、いつかそのおこぼれは消えちゃうでしょう?曲を作り続けるのは邦楽界にとってもいいことなんだろうと思うんですね。まだこれから邦楽がいろんなことをやる可能性が興るかもしれないということでしょう?
だから、演奏の伝承があるように作曲の伝承もあると思うんです。それは長唄を作るのかもしれないし、新しい、長唄じゃないものを作るのかもしれないし、あるいは長唄というものだけど新しい長唄を作るのかもしれないし。でもとにかくやり続けていかなきゃいけないと思う。それから、数がないといいものが出てこない。名前の残っている作曲家が何人かいるけれども、いっぱいいた中から彼らが残ってきたわけだし、彼らにしてもいろいろなところから引用もしている。そうするとその引用元を作った人がいるわけですよ。それを考えていくと、ものすごい量の新曲があったはずなんですよ。
今の人が曲を残そうとするなら、ものすごい量の曲を作らなきゃいけない。その作品は消えちゃっても、それを誰かが引用したり、その影響を受けて曲を作ることもあるかもしれない。音楽って一度聞いちゃったら忘れないでしょ。記憶のどこかに残っていて、聴く前には戻せない。何パーセントかにはなるんですよね、後のものの。捨て石になっちゃうかもしれないんだけど、それを恐れない。
(2017年7月19日 本郷・東大学食にて)