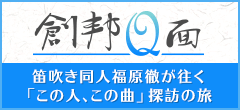笛吹き同人福原徹が活動中の10人の仲間を巡る旅、題して創邦11面相。
今月は成城学園前に今藤長龍郎を訪ねる。
今藤長龍郎篇
すべては自分の糧である [後篇]
流れを大事に
――長龍郎さんは子どもの時にピアノで作曲をしていたということですが、それと、三味線の、邦楽の作曲をするのと、ご自分の中では同じような作業なんですか。
長龍郎:あんまり分けては考えてないですけど・・・最初は邦楽曲を作るときにも、ピアノの前に座って録音しっぱなしでポロポロ弾いて、いいメロディーがあったら止めて巻き戻して書き留めてそれを膨らませていこうみたいなことをやったんです。けれども三味線の曲を作るのにピアノでは、出てくるのはあくまでも洋楽のメロディー型であって、三味線にはイマイチ乗っからないなっていうのがだんだんわかってきて、三味線を持って作るようになりました。最近は全く楽器を持たず、専らファミレスで頭で考えて作って、替手とかも全部とりあえず下書きの譜面が出来上がってから、家で弾き唄いしてみて、おかしい所、頭で考えていたのと違って流れの悪い所やなんかを手直し。清書しながら直していくっていうか。今はそういう作業ですね。
――創邦に入られて、どんなかんじでした?
長龍郎:みなさん、どうしてこんなに頭がいいんだろうって思います。どうしてこう論理立てて説明が出来るんだろうって。
――それは何、作った曲に関して?
長龍郎:曲に関してもそうですし、普段の例会でも。みんなすごいなって思います。ま、理詰めな人、理詰めなようで理詰めじゃない人、いろいろいらっしゃって、また作る曲もいろいろですけどね。生きざまと作る曲って似てますね。作った人の性格というか人間性がよく表れてます。こだわりとか。
――長龍郎さんはこだわる方ですか?
長龍郎:ぼくですか?こだわんないですねえ。ぼくはほんとに、何でもウエルカム。流れには逆らわない。20代の時はもう少しこだわってましたけど。ぼくのひとつのスタンスは、曲を作って、一緒に演奏する人が間違えたりすると、その間違えてる方が自然な流れなんだと思うんですよね。ぼくは演奏者任せなところがあって、素材で書くけど、違う方向に行ったら「あ、そっちにしましょう」ってする。音でも。間違えるってことは自然な流れではないってことです。自然な流れではないけど「そこ」に行きたいんだったら、その一個前をもうちょっとなんとかしとかなきゃいけないわけですよ。ガイドラインを足したりして。それが、美治郎さんの曲だとそういうことが絶対ないんです。絶対この音しか声が出せないっていうようになっている。
同人を語る・語る・語る
――同人の曲の話がちょっと出ましたけど、長龍郎さんからは、創邦の他の人の作品ってどんなかんじに見えます?
長龍郎:そうですねえ、ま、生まれた順で、まず政太郎さん。政太郎さんの曲って、からだにすんなり入ってくるっていうか、新作でありながらどこか懐かしさもある。とにかく曲がおいしくできている。
一方、淨貢さん。淨貢さんはもう、理詰め。ここはこういう効果を狙っている、だからこそこういうふうにするんだ、演奏家の人たちはこういうふうにやってくれ、って、もう練習の初日から指示を出せる。それが、淨貢さんの譜面を見ると、わかる。譜面を書いている段階でもうヴィジョンが出来上がっている。で、これはまた淨貢さんのすばらしさなんですが、論理立てた作曲。合同曲の時であっても、自分がどういうふうにすべきかを考えてらっしゃる。「ここでぼくが面白いことしなきゃ、この曲盛り上がらないだろ」って。だからすごい長棹の三味線を作って来たり、アイディアマンですね。
敏子さんは、聴いていて違和感のない音楽。ふわっとしてて耳に心地いい。よくフレーズを繰り返されますけれど、その間に自然と曲が深くなっていきますよね。あと音色を大事にしてらっしゃいますね。
・・・これ、いいですか、作曲の人ひとりずつ言っちゃって?
――どうぞどうぞ。ぜひ。
長龍郎:では。美治郎さんは、いつもご自分では「僕は作曲が苦手でねえ」なんておっしゃるけれど、美治郎さんも唄がおいしいんですよねえ。それは美治郎さんが唄がお好きなんだと思う。ご自分では唄は得意じゃないんだっておっしゃるけれど。唄がおいしくて、あと、唄い手を想像して曲を書いてらっしゃるなあと。なので、美治郎さんの曲って(杵屋)秀子さんが目に浮かぶ。それから「昔話シリーズ」なんて徹底的にくだけているけど、くだけた曲を書くのって、一番難しいんですよ。クドキを書くよりも実は難しくって。美治郎さんの曲は、譜面を見ると曲の流れが見えてくる。くだけたところは、なんかくだけたように書いてあるんです。クドキのところはクドキの匂いを出して書いてある。譜面を見るとノリが出てくる。似顔絵とか物まねとかがお上手なのと通ずるものがありますね。
徹さん。徹さんは、現代的でありながら、いい意味で古典ベースなんですね。なので、共演者は絶対に「ド古典」の人をお頼みになる。打ち物系なら例えば(望月)左武郎さんとか(梅屋)右近さんとか。実はそういう人たちの方が、創作・新作の場合は説得力があるとぼくは思うんです。例えば「ヨー、ポン」、その説得力ある空間を徹さんは大事にしてらして、だからこそ楽器をいつも小編成で作って、混ざるすばらしさもあれば、それぞれの楽器の味を消さないようにする、そういう曲を作ろうというこだわりがあるのかなって。すみません、へたくそな言い方で。
――いえいえ、光栄です(笑い)。
長龍郎:巳太郎さんは、エンターテイナーっていうか。それでコンテンツに合わせて見事に作り分けますね。創邦の曲は、ご自分でおっしゃっているんだけど「楽しんで作らないとね」って。「楽しい曲を書かないと、お客さんも楽しめないでしょ」って。お客さん目線の曲に行くか、プロ目線の曲にするのか、そのときのニーズをよくわかってらっしゃっていて、その通りなさる。やっぱり歌舞伎っていうニーズあっての商業演劇で研鑽を積んできた巳太郎さんだから、そういう曲を生み出しているんではないかなと思いますね。だから、ある意味巳太郎さんも淨貢さんと同じで理詰めなんですね。ただ巳太郎さんと淨貢さんとは、理詰めなんだけど表現方法が違う。淨貢さんは「理詰めだよ、ここは」って曲を出すところを、巳太郎さんは敢えて理詰めなところを理詰めっぽく見せないで作っていたり。で、ぼくらが「あの曲のあそこって?」って訊くと「わかった?誰もわかんないと思ったんだけどなあ。これのね、この場面はこうだからチョット私の解釈でこうしたんだけど」みたいに言う。あと、巳太郎さんのすごいところは、これは忠一郎さんもそうだけど、絶対に期限より前に曲が仕上がっている。やっぱり現場で、短期間で曲を作らなきゃいけない中で山積みのものをこなしてきている人なんだと思っています。
栄吉さんは、・・・なんだろうなあ、いろいろあり過ぎてまとまらない(苦笑い)。「ド古典」となると突然ド古典に行くし、かと思うと『触草』みたいな、全く古典の匂いをさせない曲もある・・・そう、栄吉さんは、自分のパートは絶対難しく書かない(笑い)。ズルいなって思うんだけど(笑い)、ほんとは弾きたくないんですって。ぼくとかは自分が弾いてナンボなんですけれども、栄吉さんは自分は聴いていたいって。栄吉さんの音の重ね方っていうのは、けっして洋楽かぶれとかじゃなくて、あれは強いて言えば「栄吉かぶれ」っていうか、いろんな音楽が混ざり合ってます。不思議なのは、弾いているそれぞれのパートのは古典的なメロディーなのに、合わせるとそうじゃないものが出来てくる。それは栄吉さんの、頭の良さっていうよりも、頭の中に駆け巡っている音楽感っていうか。だから絶対真似できない。すごいなって思います。
それから忠一郎さん。忠一郎くんはとにかくまた、忠一郎くんの辞書による、理詰めの曲。ぼくらからすると、どうしてそんなに譜面が真っ黒になるくらい書いちゃうの!?(笑い)って思うけど。それで、速いテンポで作るところとゆっくりなテンポで作るところが、普通の人と真逆。真逆の組み立て方をしますね。ここをもっと引っ張ればちょっと艶っぽくなるかなっていうところを、それが彼の性格っていうか生き方なんでしょうが、こっち向いて人の目をじっと見つめるんじゃなくて、人に背中見せる。で、背中がドヤ顔してるっていうか。
――ハッハッハッ。
長龍郎:譜面ヅラもドヤ顔してますよね。「どうですっ」て。それだから、忠一郎さんは自分の曲を暗譜するわけですよ。ドヤ顔な曲を作るんだったらドヤ顔に行くまでのプロセスがあるはずなんで。で、彼のすごいのは、「本当はこうだ」とか「こういう手だったんだけどこうした」とか、プロセスを事細かに全部覚えているんですね。ただ、最近ちょっと変わってきたのは、演奏家に少し任せてくれるようになった。前は、なにしろ自分の辞書で「これでお願いします」でしたから。彼は唄も三味線も好きで、毎回曲を作ると燃え尽きているんだろうなって思いますね。余力を残しているんじゃなくて。
それと、政貴さん。ぼくは唄でもつい器楽的に作曲してしまって、それが良くないなあとも思っていて、そういうぼくからすると、政貴さんは唄の演奏家だから三味線をはずた唄の節付けであってもどこか三味線と関連があって、自然で、なるほどと思うことがあります。前回(第12回演奏会)『清しき花』を一緒に作曲していて、特にそう感じました。あと、演奏スタイルもそうですが優しい。でも実は辛口ですよね(笑い)。
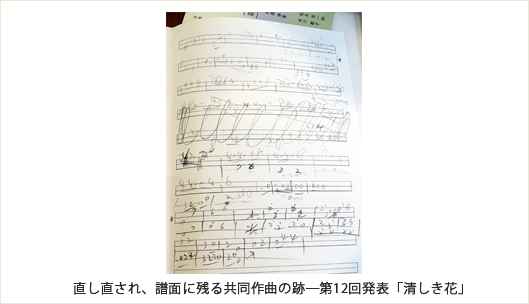
みんなが楽しくあるような
長龍郎:創邦の同人皆さんそれぞれがおもしろくて、繙いていくともっとおもしろいんで、こういうそれぞれのカラーをお客様方が分かるように、ぼくら自身が噛み砕いて全面に出さないといけませんね。プレイヤーでありながらクリエイティブな創作をしている、ほんとに稀有な会なので。もっとお客様に来ていただきたいですし。ただ、ま、ひとつ言えることは、力を入れて作曲するのはもう大事なことだと思うんですけど、全員がメインディッシュな作品になっちゃうとお客さんは疲れちゃうんで、そういうことも考えてお客さんも演奏者も楽しさを共有できるような公演がいいと思う。演奏家がみんな眉間にこう皺寄せて怖い顔して弾くんじゃなくて、お客さんたちがニヤッとしたりイスから背中がバッと離れて前のめりになる曲があったりいろいろあって、全体としてそういう意味で「楽しかったね」、そしてそれぞれの曲が「いい空気感だったね」っていうように、創邦としてもですし、自分単体としてもやっていかなきゃいけないんじゃないかなって。とかく創作の演奏会って、全部がサーロインステーキみたいになっちゃうんで、疲れちゃう。別に古典ぽいから創作じゃないかっていうと、そうじゃないと思うんです。古典のメロディーでも創作だと思いますし、現代的な何かでももちろん創作。なので、そのバランスがいい公演ができれば、お客さんも疲れないし。
あと、自分における曲作りのことですが、たとえば西洋音楽でのヒンデミットだとかちょっと理解に苦しむような曲もいいかもしれないですけど、それからとかく弾き手・唄い手を選ぶような曲も、もちろんそれはいい意味での曲の格は上がるかもしれないですけど、ぼくとしては、そうじゃなくって極論ですけど『勧進帳』みたいな曲、『越後獅子』みたいな曲が書ければいいなと。すんなり入ってきて、こう・・・
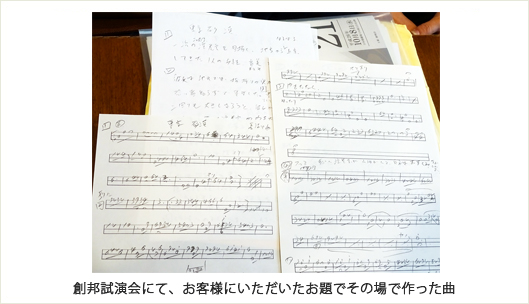
――弾きたくなるような、唄いたくなるような・・・?
長龍郎:そう。そして足さなくてもいい、引かなくてもいい曲。だから創作をやればやるほど、古典のすばらしさを感じます。古典はことばもすばらしいし、ことばに対する音の載せ方が抜群なのでね。このバランスっていうのがまだまだ自分は未熟で、どうしても新しい匂いがしなきゃいけないって肩に力が入っちゃってるような曲を作っちゃうんですが、そうじゃなくってね。とんがった曲ももちろんぼくは大好きなんだけど。これは自分が少し年取ったから思うのかもしれないけど、なんか肩の力がふっと抜けて弾ける、聴ける、そういう曲を書ければなあと。ただ、やっぱりある程度練習すれば誰でも弾ける、それが大前提だと思います。難しすぎちゃうとテクニックの羅列になっちゃって、演奏者は満足しているんだけどお客さんは疲れるだけってなる。だから、さっき言ったみたいな曲が1曲でもいいから、ぼくが死んだあとに長龍郎作曲で残ってくれればなと、思いますね。
――それが目標ですか。
長龍郎:夢です。ま、ほんと言えば2曲(笑い)。古典系の曲と現代曲で1曲ずつ。欲張りですけどね。

(2015年7月18日 成城学園前・上島珈琲店にて)
ききて:福原徹、記録:金子泰